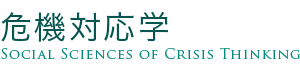東北大学小野田研究室×危機対応学 第1回意見交換研究会の記録
9月30日に、東北大学小野田泰明氏の研究室(大学院工学研究科都市・建築学専攻建築計画研究室)と、危機対応学釜石調査チームからの数名とで、意見交換研究会が行われました。

小野田氏は釜石市復興プロジェクト会議委員および復興ディレクターとして、復興計画の策定、「かまいし未来のまちプロジェクト」を通しての学校や災害公営住宅の建設、各種審査委員会などに携わって来られました。また、同研究室助教の佃悠氏は高齢者の住まいを研究されてきており、釜石市の地域包括ケア推進アドバイザーを務めたり、災害公営住宅の設計や調査に尽力されたりしてこられました。
当日は小野田研究室からは、佃氏から釜石市の災害公営住宅におけるリビングアクセスをはじめとした工夫の紹介と、石巻市での調査に基づく災害公営住宅の戸数計画の課題の指摘、修士課程の南澤恵氏から石巻市と釜石市での災害公営住宅調査の報告、修士課程の尾瀬優香理氏から学校建設と慰霊施設の検討委員会の議事録分析の報告があり、最後に小野田氏から復興計画の実装にあたっての様々な困難と工夫が紹介されました。社会科学につながる、制度上・組織上の多くの課題への言及がありました。
危機対応学からは社会学分野の4本の発表があり、吉野英岐氏(岩手県立大学)から釜石市での(小野田研究室とは異なる)災害公営住宅調査に基づく課題の指摘、大堀研氏(東京大学)から釜石市における市民活動の動向の紹介、竹村祥子氏(岩手大学)から1950年代以来の釜石における社会学系調査の歴史と昭和8年の三陸大津波を経験した女性へのライフヒストリー調査の紹介、石倉義博氏(早稲田大学)・西野淑美(東洋大学)から釜石市A町内会の被災者に震災以降毎年継続しているパネル聞き取り調査の紹介がありました。
それぞれの報告の合間には、玄田有史氏(東京大学)の和やかな司会のもと、活発なコメントが行き交いました。
お互い長年釜石に足を運びながら、じっくり議論する機会がなかった建築分野と社会科学分野の研究者が出会った初の機会。同じ地区の復興事業、同じ災害公営住宅などであっても違うデータや視点が出されることは新鮮な刺激であり、台風も迫る中、時間が全く足りなくなる盛り上がりようでした。様々な立場や視点から釜石の復興を見てきたメンバーの情報を交換することで、これまでの震災復興の道のりを多角的に捉えていくべく、今後とも研究交流を模索していくことになりました。