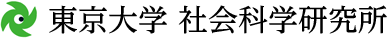案内
新刊著者訪問 第15回
『企業買収と防衛策』
著者:田中亘
商事法務 2012年:7000円(税別)
このページでは、社研の研究活動の紹介を目的として、社研所員の最近の著作についてインタビューを行っています。
第15回となる今回は、商法・法と経済学を専門分野とする田中亘准教授の『企業買収と防衛策』(商事法務2012年12月)をご紹介します。

- <目次>
- 第1章 序 論
- 第2章 敵対的買収に対する防衛策についての覚書
- 第3章 買収防衛策の限界を巡って
――ニッポン放送事件の法的検討 - 第4章 デラウェア州の買収防衛法理
――ニッポン放送事件に適用された場合 - 第5章 買収防衛策と判例の展開
――ニッポン放送事件からの流れ - 第6章 ブルドックソース事件の法的検討
- 第7章 企業価値研究会報告書の検討
――デラウェアの影、そして影との戦い - 第8章 買収防衛策イン・ザ・シャドー・オブ株式持合い ――事例研究
- 終 章 買収防衛策から公開買付規制へ
- 初出一覧/事項索引/判例索引/欧文判例索引
――本書は、2005年から2009年にかけて発表された論文に、10年にわたる研究成果を基に新たに書き下ろしの論文を加えた先生の初の単著だそうですが、すごい大作ですね。早速ですが、本書の概要についてお話下さい。
本書は、日本の上場会社を対象とする敵対的買収およびそれに対する防衛策に関する現行法の法規制について分析・検討したうえで、今後の適切な法規制のあり方について論じるものです。敵対的買収と防衛策に関するわが国の実務と法は、2000年代以降に急速に展開しました。500社を超える上場会社が、「事前警告型防衛策」と呼ばれる防衛策を導入するとともに、ニッポン放送事件やブルドックソース事件といった著名な敵対的買収事件が起こり、それに対する防衛策の適法性を巡り、重要な裁判例が現れることとなりました。
それらの裁判例は、もとより現行の法制度の枠内で防衛策の適否を判断したものであり、そこで展開された法解釈の妥当性は、本書の各章で詳しく論じています。けれども、私は、敵対的買収と防衛策に関する問題の解決は、究極的には、対象会社の株主が買収に対する賛否の判断を適切に行うことを可能にするための公開買付規制の強化を行うと同時に、防衛策については、これを禁止するという内容の立法によって行うことが望ましいと考えています。その理由は、第1に、敵対的買収、あるいはそれが起こる可能性があるということは、株式の所有構造が分散した上場会社において、経営陣を規律づけ、ひいては株式会社制度の効率性を支える重要な要素であると考えるためです。そのような敵対的買収の妨げになる防衛策は、基本的に認めるべきではないと考えます。
その半面、第2に、上場会社を買収する方法について比較的穏やかな規制しか課さない現行法のもとで、単純に防衛策を禁止するだけですますことには問題もあります。それは,買収は、その手法によっては、対象会社の株主に対して株式を売却するように圧力を加える効果――これを「強圧性」といいます――を持ちうるからです。たとえば、買収者が取引所市場での株式の買い集め――いわゆる「市場買付け」――により、対象会社の株式の過半数の取得を試みたとします。この場合、もしも対象会社の株主が、買収によって対象会社の企業価値、ひいては株式の価値が低下すると信じたとすれば、そのような会社の少数株主になることを回避するため、市場で株式を売却し、その結果、かえって買収は実現しがちになってしまうかも知れません。そのため、買収手法について適切な規制を課さないまま、買収の成否を株主による株式を売却するかどうかの判断に委ねることは、必ずしも妥当とはいえません。そこで、英国の買収規制を参考として、このような強圧性を防止するための公開買付規制の改正を行ったうえで、防衛策を禁止することが望ましいと考えます。これが、本書の考察の結論となります。
――先生は1996年法学部卒業とのこと、企業買収法については、どういうきっかけで関心を持たれたのですか?
私は、1996年に東京大学法学政治学研究科助手として、商法・会社法の研究を始めたのですが、その当初から、アメリカ会社法に関心を持ち、判例・学説を勉強していました。アメリカでは、昔から敵対的買収を含めたM&A取引が盛んで、それに関連する判例・学説も数多く存在します。その意味では、研究生活の当初から、敵対的買収を含めた企業買収法について関心を持っていたといえるでしょう。
ただ、本書の元になる論文を執筆する契機になったのは、当時シカゴ大学のシュライファー(Andrei Shleifer)とハーバード大学のサマーズ(Lawrence Summers)による論文 ”Breach of Trust in Hostile Takeovers” を読んだことでしょう。この論文の主要な主張は、企業のステークホルダー、特に長期雇用の従業員は、その企業の事業・組織に特化した技能を形成するなどいわゆる「企業特殊的人的投資」をしていることが多いが、敵対的買収は、ステークホルダーがそうした投資をするインセンティブを阻害するので望ましくない可能性がある、ということです。それはどういうことかというと、通常、こうした投資は、明示の契約に基づいて行われることは少なく――どういう投資をするかをきちんと契約に書き込めないこと、仮に書き込んだとしてもそれを履行したかどうかを裁判所に対して立証することが困難なこと、が理由です――、企業とステークホルダーとの間の「暗黙の信頼関係」に基づいて行われることが多い。従業員は、その旨の明示の契約がなくても、企業特殊的な人的投資をすれば、企業は昇進・昇給等で報いてくれると信頼して投資をしますし、企業もまた、実際に昇進・昇給の形で従業員に報いる、というわけです。ところが、敵対的買収が自由に行える場合には、従業員の信頼を裏切って、企業特殊的な人的投資をした従業員の賃金を下げるような行動――「信頼の裏切り」と呼ばれています――によって利益を挙げる目的で、企業を買収しようとする者が現れるかもしれない。そういう目的での買収が増えると、従業員等のステークホルダーは企業特殊的な人的投資をするインセンティブを失い、企業価値が低下してしまうかも知れない、と論じるものです。
――なるほど。ポイントは「ステークホルダー(株主以外の利害関係者)」ですね。
シュライファーとサマーズは経済学者ですから、法制度に関しては特に議論していません。しかし、彼らの主張は、少なくとも理論的には、敵対的買収の対象企業の取締役会は、ステークホルダーとの間の「暗黙の信頼関係」を守るため、防衛策を行使できるようにするべきだ、という法律論の支えになり得るものです。以前から、私は、株式会社を株主と取締役の関係と狭く捉えるのではなく、従業員を含めたステークホルダーの相互関係と捉える見方に共鳴していたものですから、彼らの主張が魅力的に見えまして、これを生かした法律論ができないかと考えるようになりました。これが、本書の元になった論文の中で一番古いものである「敵対的買収に対する防衛策についての覚書」(初出は2005年、執筆は2004年終わり頃)の直接の執筆動機になりました。この論文の中で、シュライファーとサマーズの主張は、企業の現経営者と敵対的買収者の選好について非対称的な仮定を置いて初めて成り立つ――その意味で、やや無理のある――主張であると評する向きがあるけれども、実は、非対称的な仮定を置かなくても彼らの主張は成り立つのではないかとコメントしている箇所があるのですが(本書72-75頁)、実は、ここがこの論文でいちばん書きたかった部分であり、他のすべての部分は、論文の体裁を整えるために後からつけ加えたといってよいものです。

田中亘(たなかわたる)
東京大学社会科学研究所准教授
専門分野:商法・法と経済学
主要業績
『企業買収と防衛策』(商事法務、2012年)
『数字でわかる会社法』(編著、有斐閣、2013)
『会社法(第2版)』(共著、有斐閣、2011)
『事例で考える会社法』(共著、有斐閣、2011)
もっとも、「ステークホルダーとの暗黙の信頼関係を守るために取締役会は防衛策を行使すべきだ」という主張は、確かに理論的には成り立ちうるけれども、実際にこういう主張に基づいて法制度を作るべきかというと問題があります。対象企業の取締役は、ステークホルダーの利益を守るために適当な主体かどうか、防衛策を認めるとかえってそれを自己の保身のために利用するのではないか、といった問題がありうるからです。本書も、結論としては、対象企業の取締役会はステークホルダーのために防衛策を行使できるという主張には否定的な立場をとっています(本書382-383頁)。とはいえ、自分自身の中に、ステークホルダー論への関心が常にあって、それが、本書に限らず、会社法関係のいろいろな研究の一つの契機になっていることは間違いありません。
――本書の刊行(2012年12月)直後に第2次安倍内閣が発足し、アベノミクスという大胆な経済政策により経済が急展開していますが、今後、敵対的買収あるいは買収防衛実務はどうなるとお考えですか?
日本では、敵対的買収に対するステークホルダーの抵抗感が強く、たとえ法律上防衛策を厳しく規制したとしても、敵対的買収がアメリカ並みに広く行われることは考えにくいと思います。ただ、本書でも触れていますが、90年代末以降の日本では、海外投資家を初めとする機関投資家の株式保有が急増しており、特に大規模上場会社では、機関投資家が株式保有の過半数を占めるようになっているところが多いです。こうした会社では、経営陣・取締役会も投資家株主の意向を無視できないでしょうし、明確に敵対的とはいえないとしても、株主の強い意向が反映した形で買収が成立するケースが今後は増えていく可能性があると考えています。
(2013年9月20日掲載)