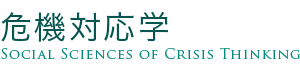考えたくないことを、誰がどう考えるか? ―「ネガティブ・ケイパビリティ」と危機対応学―
死刑囚の朝は恐怖に満ちているという。近づいてくる刑務官の足音が、自らの独房の前で止まるかどうか。止まればその日のうちに刑が執行される可能性が高い。毎朝の恐怖は極度の不安と緊張をもたらし、ついには精神に異常をきたしてしまうこともあると聞く。
では、塀の外に暮らす私たちの毎日は、死刑囚のそれといったい何が異なるのだろうか。一見まったく異なるように思えるが、パスカルも指摘するように1、実はそれほど変わらない。死は、すべての人間に必ずやってくる。しかしそれがいつなのかは、容易にわからない。もちろんその確率は小さいが、事故や急病によって、今日突然命を終えてしまう可能性もないわけではない。それでも私たちの多くは、そのことの恐怖や、不安や緊張を強く感じることなく毎日を過ごしている。
結局のところ、死刑囚と私たちのもっとも大きな違いは、日々の生活のなかで「死」の可能性をどれほど強く意識させられるか、の違いにあるのではないだろうか。外界からの刺激や行動の自由が制限され、関心の行き場が多くない日々を送り、いつかは必ず訪れる刑の執行、そしてそれを告げるのかもしれない刑務官の足音を否応なく意識せざるをえない独房の死刑囚と、刺激や情報に満ち、他者との交流も多い毎日を、突然自らが死に至る可能性や具体的な道筋を強く意識しなくても過ごせてしまう私たち2。そう考えると、将来起きるかもしれない悲しくつらい出来事を想像したり考えたりしなくて済むということは—それが本当に良いことなのかどうかはさておき—一種の特権のように思えてくる。
危機対応学を進めていく上で、人間のこのような心理には十分に注意を払いたいと思う。「危機」にはさまざまなものがある。しかしそのなかで本当に深刻な危機とは、その生々しいあり様を想像したり考えたりするだけで極度の不安や緊張を感じ、時に精神のバランスさえ崩してしまうものなのかもしれない。そしてこのような心理が、ひとびとの危機への対応にも影響を及ぼしているように思われる。
防災行動を例にとってみよう。その必要性が叫ばれているにもかかわらず、家具の耐震補強をはじめ、災害へのひとびとの備えは、専門家の眼からすれば十分に行われているとは言い難い。このため「大きな地震が起きたらどうなるのか」をもっと想像力を働かせてイメージし、命を守る方策を自らより深く考えることが求められたりもする。
しかし深刻な危機について想像すること自体が、緊張や不安といったネガティブな心理作用をもたらすものだとすれば、その必要性を頭ではわかっていながらも、危機的状況について実際にイメージしたり、考えたりすることに心理的な負担を感じてしまうために、結果として十分な防災行動がとられていない、と現状を理解すべきなのかもしれない。もしそうだとすれば、危機対応学は、不安や緊張を伴う「危機的状況の想像」をひとびとにもっと頑張って引き受けてもらうことを目指すべきなのだろうか。あるいは、その負担をできるだけ小さくしつつ、必要な準備を行えるような仕組みの考案を目指すべきなのだろうか。
さらに危機対応の問題に関しては、少し性質の異なる「考えたくないこと」も存在する。いわゆる「想定外」の問題がそれである3。
東日本大震災の際の福島原発事故は、想定を大きく超える津波が襲ったために生じたとされる。もちろん、津波の規模の想定が過去の事例に照らして十分でなかったことは、きわめて深刻な問題である。しかし、必要な費用の制約や対処の根本的な不可能性のために、現実的には「ここまでは発生し得るものと想定し、万全な対処を行うリスク」と「とりあえずここから先は発生しないものと想定するリスク」の線引きを、どこかで行う必要があることもまた事実である。
ただし、絶対に発生しない事象というものは、世の中にそうない。確率論的な立場に立てば、記録の上では前例がないような大きな地震でさえ、きわめて低い確率ではあろうが、やはり生じ得る。そうであればこそ、たとえ外向きには「そのようなことは起きない」と説明していたとしても、組織の内部では公式的な想定を超える事態が起こった際の対処について検討されていてもおかしくはないし、むしろ外部の人間としてはそれを強く期待してしまう。
もちろん「公式的な想定」を超える事態について考えることは容易でない。そのような事態を考えること自体への批判が生じる場合もあるだろうし4、対処の予算がほとんど確保できない場合もあるだろう。またそもそも、すでに大きな被害が発生している状況を前提とせねばならず、その重みに耐えづらい場合もあるかもしれない。組織内部のひとびとにとっても、公式的な想定を超える事態は発生しない(=問題が生じてもすべて対応可能である)と考える方がはるかに楽である。 しかし福島第一原発事故は、「万が一、公式的な想定を超える事態が発生したらどうなるか」が十分に考えられてこなかった結果、ここまで甚大な被害をもたらしてしまったのではないだろうか5。このような「考えたくないこと」の検討もまた、危機の被害を少しでも小さくするために、誰かが引き受けなければならない課題である。この課題がきちんと引き受けられるためには、何が必要なのだろうか。
ネガティブ・ケイパビリティ(negative capability)は、まさにこの「考えたくないこと」を考えるために必要な力といえるだろう。「消極的能力」などと訳されることもあるこのネガティブ・ケイパビリティを、帚木蓬生は「どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」、あるいは「性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力6」と説明する。この能力はもともと英国の詩人、ジョン・キーツが、文豪シェークスピアの持つ「理由付けや結論付けを急がず、真に創造的な創作をなす力」として発見したものであり、その後、精神分析医が先入見なしに患者に接し、患者に対するより深い理解と共感を得るために必要な能力として、注目を集めてきた7 。ネガティブ(否定的/消極的)なケイパビリティ(能力)とは一種の形容矛盾であるが、「何らかの決断や決定を行う力」としてのポジティブな能力ではなく、むしろその逆の「決断や決定を行わない(で耐える)力」を肯定的に位置づけたところがミソであろう。
「大きな地震が来たのならば、自分や家族の命も助からないだろう」と、最初から絶望してしまうのではなく、あるいはその逆に事態から目をそらしてしまうのでもなく、具体的な状況を想像しつつ、そのなかで少しでも可能な対処を考え、実践していく力。これはまさに「対処が難しい状況に身を置きつつ耐える能力」としてのネガティブ・ケイパビリティに近いのではないだろうか。
あるいは「公式的な想定」に安住することなく、対処策がまったく講じられていない想定外の事態が生じてしまう可能性を考えつつ、その重みに押しつぶされず、できる限り被害を小さくする方策を考え、実行に移していける力。このような「不確実さに耐えながら、状況改善のための努力を重ねる力」もやはりネガティブ・ケイパビリティの一種であろう。
以上のように、大きな被害をもたらす危機に対する備えや対応が、「ネガティブ・ケイパビリティ」という能力によって左右されると考えた場合、危機対応の問題に私たちはどのように取り組むべきなのだろうか。残された紙幅で、簡単に考えてみたい。
まず、このネガティブ・ケイパビリティも一種の能力である以上、そのような力を強く持つひとびとと、そうではないひとびとの間の個人差を認め、その上で、危機への備えや対応の課題を具体的に考えていくことが出発点となるだろう。
たとえば、行政機関や企業における危機対応の課題には、この「対処しようのない事態や不確実な状況に耐えられる力」を強く持つひとびとが当たることが望ましい。「ここまでは発生し得るものと想定し、万全な対処を行うリスク」と「ここから先は発生しないものと想定するリスク」の間の線引きをいったん行いつつも、自らその区分線をぼやかし、不安定な状態に耐えながらグレーゾーンについて考えていく力とは、明晰さを志向する近代科学の思考とは、あきらかに方向が異なる8。このような能力の有無は、かならずしも容易に判断できるものではないかもしれないが、そのなかでも、できるかぎりこの「適材適所」が可能となるような組織や社会の仕組みを考え、その実現を目指していくべきだろう。
一方で、個人や家庭の防災行動のように、全員が担うべき課題もある。「将来起こるかもしれない大きな災害を想像し、その上で必要な準備や対処を行う」ことが、かならずしも全員にとって容易でないとすれば、「その指針に従いさえすれば、必要な準備・対処がある程度行える」という程度にまで、必要な課題を分解してしまうことが望ましいのかもしれない。想像するだけでつらくなってしまう将来の危機から目をそらすのでもなく、逆にイメージしすぎてしんどくなってしまうのでもなく、しかし必要な対処をできる限り多くのひとびとが行えるようにするには、「悲惨な状況の想像・イメージ」とは切りはなした形で課題をシンプルにし、時にパッケージ化してしまうことが有効なように思われる9。
さらには、ひとびとのネガティブ・ケイパビリティ自体をどのように高めていくか、という課題も残っているが、それを社会的に行うことの是非とその具体的な方法論を含め、この問題は非常に大きなものであるので、機会があれば稿を改めて考えてみたい。
本プロジェクト「危機対応学」の英訳は、"Social Sciences of Crisis Thinking"。まさに「危機について考えること」を社会科学していく、という意味である。「考えたくないこと」としての危機について、誰がどう考えていくのか。また、それには何が必要であり、そのための社会的な仕組みはどのように築いていけるのか。本当の危機とは、考えたくもないような悲惨な状況かもしれない、という重みを十分に受け止めながら、さらに考えていきたい。
http://web.iss.u-tokyo.ac.jp/crisis/essay/post-3.html