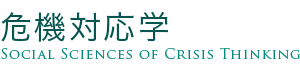「内向き社会」という危機をこえて ―Meridian 180年次大会(ブリュッセル)に参加して
今回は、ブリュッセルで開催されたMeridian 180のカンファレンスの模様をお伝えします。
危機対応学とMeridian180
Meridian 180という組織をご存知ですか?
これまで危機対応学に関するお知らせのなかにも何度か登場したことがあるため、見覚えのある方もいらっしゃるかもしれません。Meridian 180は、アメリカのコーネル大学に拠点を置く、グローバルな政策課題を議論するための専門家のネットワークです(詳しくはコチラ)。現在、39ヶ国以上から800人以上の研究者・実務家・官僚が参加し、オンラインのフォーラムや各国での研究プロジェクトを通じて様々な課題に対する政策提言に向けた活動を行っています。危機対応学プロジェクトはこのMeridian 180の理念に賛同してパートナーシップを結んでおり、プロジェクトの研究成果をグローバルに発信するための重要なプラットフォームとしてその活動をサポートしています。その、Meridian 180が年に一度開催するカンファレンス(Annual Summit)が、5月19日から21日にかけてベルギーのブリュッセルで開催されました。
実は昨年の年次大会は、沖縄で開催されています。" Developing Proposals for Risk Mitigation in the Asia-Pacific Region" というテーマのもと、普段は世界中に散らばっているMeridian 180のメンバーが一堂に会して議論を行いました。われわれ危機対応学プロジェクトはその会議の主催者側として、会議の企画から運営に協力しています。そのときの会議の様子は、危機対応学のプロジェクトリーダー玄田有史先生のエッセイ「希望、沖縄、危機対応」に詳しいので、ぜひこちらもご覧ください!
さてその沖縄会議からはや1年、今年の年次大会は"How to respond to the rise of Inward-Looking Society"(「内向き社会」にいかに対応するか)というテーマのもとブリュッセルで開催されました。日本からも社研の危機対応学プロジェクトを中心に、他の大学の先生方や実務家の方を含めて10人あまりのメンバーが参加してきました。会議では、われわれ危機対応学の取り組みをMeridianメンバーに紹介し、多くの関心と応援を得ることができました。その会議のユニークな模様を、詳しくお伝えしたいと思います。
************************************
ブリュッセルに到着して会議が始まる前、日本から参加した先生方とブリュッセルの街を歩いてみる。5月は、ヨーロッパが一番美しい季節かもしれない。日ごとに濃くなる街路樹の緑が、石造りの重厚な建物と鮮やかなコントラストをつくる。気温は十分に高く、でもカラリとしていて柔らかい風が心地よい。街にでたのはちょうど夕方に差し掛かるころで、日差しが傾いて空気がゆっくりと金色に染まるよう。ブリュッセルはヨーロッパの多くの都市と同じく、広場を中心に放射状に街路が伸びており、そうした円状の街区がいくつも境界を接しながら街を構成している。


デコボコの石畳の路地をなんども曲がりながら歩いていくと、近代的なビルが並ぶ一角があらわれる。―EU本部だ。ずらりと掲げられた国旗をみながら、この静かな街がヨーロッパという壮大なプロジェクトの中枢であることを思い出す。今回のブリュッセルでの会議開催が決まったのは1年近く前のことだと思うが、いまとなってはまるで未来を予見していたかのようだ。この1年間に起こった出来事――例えばイギリスのEU脱退やアメリカでのトランプ政権の誕生など――により私たちを取り巻く世界は想像以上のスピードで変化した。1年前、メリディアンは沖縄で来るべき「危機」について話し合っていたのだが、いまではそのとき危惧された"Inward-Looking Society"がわれわれの目の前に現実のものとして到来している。いまこのテーマについて語るのに、ブリュッセルほどピッタリの場所はない。


EU本部の建物からはつぎつぎと仕事を終えた人がでてくる。近くには大きな広場があってカフェやレストランがまわりを取り囲んでおり、仕事帰りの人々を中心に大いに賑わっている。その人達は見た目も言葉もじつに多様で、ヨーロッパ中からEUを支えるためにここブリュッセルに集まってきている人たちだ。なんて多様でオープンな社会なのだろうと感心する一方、だからこそ「内向き」への揺り戻しが大きくなる危険と隣り合わせなのかもしれないとも思う。日本との違いを肌で感じながら、それでもグローバルに社会をおおう「内向き化」の流れを思って、これからはじまる会議の意味に思いを馳せた。
"危機を無駄にするな!"
次の日、会議はキーノート・スピーチで幕を開けた。スピーカーは、初代EU大統領(欧州理事会議長)のHerman Van Rompuy氏。ブリュッセルでこれからのグローバルな協力のあり方を探ろうという私たちの会議の趣旨に照らして、これ以上の素晴らしいめぐり合わせはない。


講演のタイトルは、Europe in the Storm(激動のヨーロッパ)。彼は、いまの世界をおおう問題のひとつとして、なにかの「機能不全」に対する批判が、容易にその「存在」そのものに対する批判に横滑りしてしまうことの危険性を指摘した。たとえば、「EUがうまく機能していない」ことに対する批判が、そのまま「EUには価値がない」という批判に横滑りする。あるいは、「民主主義がうまく機能してない」ことに対する批判が、そのまま「民主主義はダメだ」という批判につながってしまう。そして何かがうまく「機能している」かどうかは、しばしば経済成長など別の目的の役に立っているかどうかで判断されてしまう。しかしながら、民主主義は経済成長の役に立つから価値があるのではなく、その存在自体のうちに価値があることを見失ってはならない、ということであった。
もう一つ、彼のスピーチの中でわたしたち危機対応学プロジェクトにとって忘れがたいフレーズが、Never Waste Good Crisis!(危機を無駄にするな!)というものだ。もともとはイギリスの首相、ウィンストン・チャーチルの言葉だという。チャーチルが第二次世界大戦の危機のなかに来るべき新たな世界を引き寄せるためのチャンスを見出そうとしたように、こんにちのEUもまた、その存在の危機に直面して初めてこれまでになく結束を強めている。このフレーズは、私たち危機対応学プロジェクトの信念――「『危機』は、危険(risk)の『危』と、機会(opportunity)の『機』の両方から構成される言葉である。」「危機に対応するとは、危険を回避したり極小化するということだけでなく、それによって新たな機会を創り出そうとするものでなければならないはずだ。」(玄田有史先生)という主張に深く共鳴するものだと感じた。そしてVan Rompuy氏は、「だから、いまのヨーロッパの状況にSense of Urgency(危機感)を持つことは必要なのだが、それでも私は希望の人(Man of Hope)でありたい」、とスピーチを締めくくった。心のなかに温かい希望がにじんでくるような贈り物だ。
余談だが、このVan Rompuy氏は日本の俳句に造詣が深く、みずから英語で俳句をたしなみ、これまで2冊の句集を出版している。英語で俳句とはと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれないが、英語の俳句は日本語のように文字で数える代わりに、Syllables(音節)でカウントするらしい。例えば彼の句は、
Brussels:
Different colours,
tongues, towers and gods.
I search my way.
(訳)ブリュッセル:
いろんな(肌の)色、
言語、宗教・・・
私は自分の道を探している
・・・という具合である。かつてVan Rompuy氏はインタビューに答えて、政治は生き馬の目を抜く世界だからHaiku Poemの静謐な世界に身をおくことで心のバランスを保つのだと話している。EUという前代未聞の大プロジェクトのトップとして、どれだけの危機(ピンチ)を乗り越え機会(チャンス)を拓いてこられたのだろうかと、その功績を思った。
「ことば」の檻と「翻訳」のチカラ
前回の沖縄会議もそうだったが、Meridian 180の会議のプログラムはとてもユニークだ。参加者がただ席について議論を交わすのではなく、会場を歩き回ったり、身体を使ってパフォーマンスしたり、あえて共通点のない人と思いもよらないテーマについて話すといった、一風変わったワークショップから構成される。これは、普段は顔をあわせることのないメンバー同士の交流を一気に深め、対話を促進し、課題への新たなアプローチを探りたいという狙いからくる。
初日の夕食の会場は王立美術館のホールで、古代シリアの彫刻に囲まれながらのワーキングディナーだ。会場につくと、それぞれのディナーテーブルには会議のテーマである"Inward-Looking Society"にちなんだキーワードが置かれている。キーワードは、Curiosity(好奇心)、Tolerance(寛容)、Risk(リスク)、Discovery(発見)、Hope(希望)、The Gift(贈り物)、The Stranger(見知らぬ人)、Planting the Seed(種をまく)、Diversity(多様性)、Dialogue(対話)、Trust(信頼)。 各自がもっとも関心のあるキーワードのあるテーブルに着席するよう求められる。ディナーの間、そのキーワードとInward-Looking Societyの関連について議論し、食事の終わりにプレゼンテーションを行う。


たとえば私の着席したテーブルのキーワードは"Tolerance"。私たちは順番に"Tolerance"という言葉にちなんだ経験を話していく。面白いことに、Toleranceという言葉に対して持っているイメージは各人でかなり異なっている。試しに、それぞれがToleranceという言葉をジェスチャーで表現してみる。すると、英語が母国語の人は、手を前に出して何かを押し戻すような仕草をする。彼らにとってToleranceは苦痛に耐える、我慢する、というニュアンスだ。中国語が母国語の人は、胸をおさえたり切りつける仕草をするが、これはToleranceが「忍」という字(=心という字に刃の字)で表されるゆえだ。私はといえば、手を伸ばしてむしろ自分を他人に向かって開くジェスチャーをした。これはToleranceという言葉に「寛容」という日本語をあてて理解しているためだが、皆がそのジェスチャーは意外だと驚く。
こうした会話を通じてあらためて考えさせられたのが、私たちが何かを理解するうえでいかに「ことば」に、さらにいえば「母語」に制約されているかということだ。いうまでもなく、私たちは言葉を通じてしか、世界を理解することができない。外国語を理解するとき、別の言葉(母語)で切り取った世界を当てはめて理解するしかなく、もとの言葉を直接に理解することはできない。かといって、それは母語を通じて知っている世界とまったく異なるわけでもない。重複があって、差異がある。そのズレを梃子にして、私たちは世界のあり方を立体的に重層的に理解することができる。だからこそ、母語の異なる人とこうしてコミュニケーションをすることは、自分の世界を広げるきっかけになりうる。Meridian 180はその活動において多言語間の「翻訳」をとても重視しているのだが、今回の議論はその「翻訳」という行為がもつ限界と可能性についてあらためて考えさせられた。
"オブジェ"と"ものがたり"
今回の会議において、重要な役割を果たしたのが"オブジェ"である。会議に参加する人は、事前に"Inward-Looking Society"を象徴する身の回りのもの(オブジェ)をなにか一つ選び、それを会議に持参することになっていた。さらに、各自がそのオブジェを紹介する30秒ほどのビデオクリップをスマートフォンなどで撮影して、そのビデオが会議の専用アプリを通じて皆に共有されていた。
たとえば、玄田有史先生が選んだオブジェはポータブルラジオ。事前に作成されたビデオはこんな具合だ。
これはポータブルラジオ。毎日ラジオから流れてくる音楽が、私をInward-Looking Societyから連れ出してくれます。海外に行ったときには、ローカルのラジオ局を聞くのが好きです。震災の直後、ラジオは個人的な信頼のおける情報を私たちに伝えてくれました。このラジオはとても壊れやすいのですが、私のポケットにはこれからも新しいラジオが入っていることと思います。
私が選んだのは、カラフルなモビール。このオブジェに、こんな想いを込めた。

これは、小さな娘に買ったペーパーモビールです。これを見ていると、カラフルで、たえず動いてひとところに止まらず、まるで私たちの「社会」のよう。子供のような無垢な好奇心と想像力をもって豊かな現実を楽しむ、自分の中の「内向き社会」を乗り越えるために、私はそういう気持ちを大事にしていきたいと思う。
参加者が選んだオブジェには、それぞれに個人的なストーリーがあり、思いがあり、世界との関わり方があり、とても興味ぶかい。
※会議に向けて参加者が作成したビデオクリップがご覧いただけます。(コチラから)
さて、会議の2日目に、参加者がそれぞれに持ち寄ったオブジェをテーマにしたワークショップが開かれた。まず2人組をつくって、相手にオブジェを見せながら、それがいったい何なのか、自分にとってどういう意味を持っているのか、なぜそのオブジェが"Inward-Looking Society"に関連すると考えたのか、言葉で相手に説明する。「もの」について「語る」、まさに文字通りの「ものがたり=Story Telling」だ。ストーリーを聞いた相手は、自分が聞いた話のなかからパートナーの真実(Truth)に迫る3つのキーワードを選ぶよう求められる。そして最後に、グループのメンバーに対してそれをジェスチャーとともにプレゼンテーションする。


私がペアを組んだ相手のオブジェはHorseshoe(馬蹄)だった。それは錆びついていて、手にとってみるとずっしり重い。彼は、自分の母や祖父母がオーストラリアで育ち、馬がいつも生活の一部としてあったことを話してくれた。馬は家族のルーツ、家族の親密さの象徴だ。ではなぜ、その馬が"Inward-Looking Society"と関係するのかというと、その昔、馬にのって駆けることは街の境界(Border)をマークする行為だったからだという。なるほど、トランプ政権の誕生以降アメリカにおいて、自分たちの社会に境界線を引くという行為は、特別な意味を持っている。彼は、これまで親しんだ馬蹄にこんにちの排外主義的な思想を重ねて複雑な気持ちのようだ。
そこで私は彼の話から、Intimacy(親密さ)、Ambivalent (相反する感情)、Proud(誇りに思う)という3つのキーワードを選んだ。最後の"Proud"は、彼自身は使わなかった言葉だが、家族の話をするときの彼の様子から彼が誇らしく思っているらしいと感じて、あえて付け加えた。すると、彼はそのことを取り上げて以下のようフロアにむけて語った。
自分のストーリーが彼女によって語られたことによって、それは自分だけのストーリーではなくなり、彼女のストーリーにもなった。でもここで、ストーリーが誰のものかを問題にしたいわけではない。ストーリーとは、誰かに所有されるべきものでもないからだ。私たちはみなストーリーを語ることによって、自分を、世界を、理解する。たったいま自分は、自分のストーリーが別の人に語りなおされたことによって、自分では明確に意識していなかった自分の一面をあらたに発見することになった。
考えてみれば、私たちはプライベートでも仕事においても、日々誰かのストーリーに耳をかたむけ、それを自らの言葉にかえて社会に語り直すという行為を行っている。研究者や弁護士など専門家といわれる人なら、なおさらのことだ。このワークショップを通じて、他人のストーリーを引き受けるとはどういうことかについて考えさせられた。なにが誠実な語りなのかと考えることを、忘れないようにしたいと思う。
さて、その後オブジェたちはどうなったかというと・・・このあと会場では自分のオブジェを他の人のオブジェと交換するためのオークションが行われて、大いに盛り上がった。世界中から集ってきたオブジェは、誰かに引き取られて再び世界中に散らばっていくことになる。皆のオブジェにまつわるストーリーはこの会議で「ものがたられ」、誰かに語り直され、そしてまた世界のどこかであたらしいストーリーをつないでいくことになるのだろう。


専門家と"パフォーマンス"
さて、ここまでご紹介したのは、会議の参加者が一堂に会して参加する全体セッションの様子である。会議の期間中、約半分の時間はこの全体セッションからなるが、残りの半分は4つの専門部会に分かれて専門的な議論を深める時間にあてられている。4つの専門部会のテーマは以下のとおりである。
1) Migration(移民): Cultural homogeneity and Migrations
2) Energy(エネルギー): Energy cooperation, dependence and appreciation
3) Trade(通商): Local prosperity and global sustainability
4) Security(安全保障): Security at home and peace abroad
会議の参加者はそれぞれどの専門部会に参加するかを事前に選択している。各部会に議長が決められ、それぞれの部会ごとのセッションをどのように運営するかを企画する。なかには事前に宿題が課されたグループもあったようだ。それぞれの専門部会ごとに別々の会議室にわかれ、午前中から昼食を挟んで午後も議論が続く。それぞれの部会には、普段からテーマを研究している専門家もいれば、自分の研究テーマとは敢えて関係の遠いテーマを選んだ参加者もいて、多様なバックグラウンドのメンバーを擁するメリディアンならではの活発の議論が行われた。




そして会議の最終日、その専門部会の議論の成果を発表する場が設けられた。この発表がまた、メリディアンの会議らしく、いわゆる普通のプレゼンテーションではなく、趣向を凝らしたパフォーマンスが続いた。 たとえばTradeのグループは、まるで演劇の舞台のように広いホール全体を使って、メンバーが一人ずつ順番に今日の貿易が直面する問題を表現するスローガンを叫びながらパフォーマンスを行う。
"公正な貿易が必要だって!?(フェアトレードなど)誰が、1杯2000円もするコーヒーを飲みたいと思うものか!"
"エリート万歳!民主主義はいらない!官僚万歳!"
"貿易を政治化しろって!?バカな奴らだ!"


意表をついたパフォーマンスに会場は湧いて、笑いに包まれた。だが、あまりに扇動的な言葉には少なからぬ人がショックを受けたはずだ。パフォーマンスが終わった後、フロアの観客はそれをみてどのように感じたか、口々に意見交換した。 また、次のMigration(移民)のグループは全員が大きな円座をつくって内側に向いて座り、一人ずつ「移民」にまつわる個人的な記憶やエピソードを語る、というパフォーマンスを行った。色んな人の語りから、「移民」という現象が直面する問題が多面的に浮かび上がってくる。それぞれの話は個人的なものでありながら、今日の移民が抱える社会的なレベルの問題につながっている。そして、まるでキャンプファイヤーを囲むように内側をむいて語り合う彼らの姿が、Inward-Looking Societyのメタファーであるかのように思えるのも面白い。


こうした一連のパフォーマンスをみながら考えさせられたのは、こんにち専門家がどのように自分たちの議論を発信し聞き手に届けるかということが問われているということだ。Post-Truthといわれる時代、真実の価値がおとしめられ、専門的で難解な議論は煙たがられる。メリディアンのメンバーも専門家として、こんにちの社会の「分断」と「内向き化」に責任と挫折を感じているに違いない。ここに集う人たちが感じているのは、専門家は自分たちの議論を専門家仲間に向けて発信するだけでは十分ではない、ということだ。社会に何かのメッセージを届けて議論を喚起するために、私たちにはどのようなコミュニケーションが必要なのだろうかということを考えさせられる一幕だった。
さて、目まぐるしく過ぎた3日間の会議も、いよいよ終わりに近づく。最終日の朝、参加者はこの会議を振り返ってごく短いエッセイの提出を求められた。全員分のエッセイが印刷され、ホールの壁にぐるりと貼り出された。みなで壁一面に連なるエッセイを読みながら、この会議が実にさまざまな気付きをメンバーにもたらしたことをあらためて確認する。Meridian 180の創設者であるAnnelise Riles先生、今回の会議の企画者であるKim Eric Monic氏が会議の締めくくりを行い、3日間の会議は幕を閉じた。私たちは、様々なワークショップを通じて親交を深めたメンバーと、別れを惜しんで挨拶を交わす。今回の会議における議論は、今後メリディアンでのオンラインフォーラムや研究プロジェクトに発展していくことになるが、その際には今回顔をつきあわせて体験を共有し議論をたたかわせた経験が、私たち一人ひとりの、またメリディアンとしての貴重な財産になっていくことだろう。
メリディアンの活動は今後も随時、危機対応学のホームページでお知らせします。今後とも危機対応学とMeridian 180にぜひご期待下さい!

【日本からの参加者による会議の振り返りをご紹介します】
保城広至 (社会科学研究所)
今回のメリディアン180会議に参加して痛く感じたことは、アメリカにおけるトランプ政権の誕生が世界に対して大きなインパクトを与えているということです。そして主にアカデミックに所属している本会議の参加者は、例外なく、その影響をネガティブにとらえていると感じました。私が参加したのは貿易セッションでしたが、自由貿易による再分配問題は、集中して取り上げられたトピックのひとつでした。そしてトランプ政権の影響として、貿易問題においても世界が内向きの方向に向かっている傾向が話し合われました。それを回避するにはどうすれば良いのか、われわれは真剣にこの問題に取り組む必要があります(残念ながら正直なところ、今の段階では解決法はわかりません)。
今回会議のテーマから見て取れるように、本会議の参加者はみな、「内向きの社会」を超える、つまり「外向きの社会」の必要性を共有しているようでした。しかしながらそのような前提自体も、実は問われるべきであるかもしれません。理論的には、すべての社会が「内向き」になれば、国際紛争など起こりようもなく、実際のところ例えば戦前期日本の大陸進攻は、「アジア主義」や「八紘一宇」と言った、極めて「外向き」のイデオロギーが背景にあったことは覚えておくべきでしょう。
ともあれ、多くの国籍やジェンダーの異なる参加者と話し合えたこと、今回会議に参加した意義はそれにつきます。
藤谷武史(社会科学研究所)
「内向き社会の台頭」を超えて
今年のメリディアン180・ブリュッセル会合の統一テーマは、近時の移民問題、ブレクジット、 トランプ現象等を念頭においた、「内向き社会(inward-looking societies)の台頭に対応する」というものであった。その企図について多言は不要であろう。世界各国から、上記の問題意識を共有しつつ、しかし専門分野・地理的・社会的背景の面では極めて多様な参加者が集い、予定調和ではない濃密な対話を重ねた3日間であった。
特に印象的だったのが、対話の中で、「この集まり(=地理的にも専門分野的にも「越境」志向の強い、「意識の高い」人々が集う、メリディアン180という場)自体もまた、一つの『内向き社会』『部族tribe』なんだよね」という冷静な省察が、複数の参加者から提起されたことである。反グローバリズムや移民排斥・極右政党の台頭のように「国家」単位を強調する傾向の強まりと、メリディアン180のような、国境や立場を超えた認識共同体(epistemic community)が叢生し活性化する現象とは、実はコインの表裏のような関係にある。すなわち、越境的エリートたちは、自国の「市井の人々」よりも、他国のlike-mindな越境的エリートとの方が遙かに円滑にコミュニケーションができ(意見の対立も対立として尊重しつつ対応できる)、居心地の良さすら感じるであろう。しかしその認識ギャップこそが、有権者の多くを「自分たちの目線で語る」ように見える政治家への支持に向かわせた面もあろう。「啓蒙的エリートが内向き社会の愚を説く」式のやり方では、(コスモポリタン・エリート共同体が嘆く意味での)「内向き社会」の流れを押しとどめることは(歴史上そうであったように大きな犠牲を払った後に皆が気づく、というのでなければ)かなり困難であろう。《「内向き社会の台頭」を嘆く》我々の問題意識のあり方もまた、克服される必要がある、ということであろう。
では、どうするか。個人的には、今回の会議における対話を通じて、「『再分配』のバージョンアップ」というキーワードを、今後の自分の宿題として持ち帰った。「再分配」というと、富や所得の再分配、という経済的な側面にフォーカスしがちであるが、それらは控えめに言っても手段に過ぎない(もちろん、グローバル経済の果実の分配が偏っていることは、極めて大きな――今更指摘するまでもないほどに自明な――問題である)。しかるに、「内向き社会」の台頭の根本的な要因は、現代を生きる人々の間に、帰属感・自尊感情・好奇心、あるいは「様々な可能性が開かれていることについての認識」、といったソフト面において、絶望的なまでの格差があることではないか(このあたり、希望学の視座とも重なる)。この差は、例えばベーシック・インカムで金銭を配ることだけでは埋まらない。インターネットや人工知能等の発展の結果、モノも情報も、それと望めば安く手に入るようになっている。しかし、「モチベーションの再分配」はいかにして可能か。ただ単に福祉国家型の再分配をグローバルに再建するのでは足りず、「バージョンアップ」を施す必要がある。そのときにはじめて、我々は「内向き社会」の克服を語るための必要条件を満たしたということがいえるのではないか。
高橋五月(法政大学)
去年の沖縄会議に続き、今年のブリュッセル会議にも参加し、前回と同様にとても刺激的で有意義な時間を過ごした。今回のテーマはinward-looking societyであったが、メリディアン・サミットらしく、頭だけでなく、体も使い、「内向きな社会」について考え、議論し、表現し、語り合った。その結果、私が改めて気づいたことは、inward-looking society is everywhereということだった。普段研究者として過ごしていると「内向きな社会」は研究興味の対象ではあっても、日常の身近な存在であるという意識は薄かった。しかし、今回ブリュッセルで過ごした3日間で「内向きな社会」がどれだけ身近な存在であるかを改めて考えることができた。そして今、「内向きな社会」の身近さに気づいたことで、「内向きな社会」に立ち向かうには外なる視点だけではなく、内なる視点も重要なのだろうと思っている。