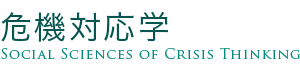危機対応の社会科学と集団科学的思考
1. 社会科学における「集団科学的思考」の重要性
生物学者のエルンスト・マイヤーは、進化生物学の発展を考察する中で、「類型学的思考」(typological thinking)と、「集団科学的思考」(population thinking)という2つの異なる考え方を対比させている1。前者の類型学的思考とは、古くはプラトンにまで遡ることが可能なものであり、個々の生物個体を構成している本質的な特徴が存在すると見なすものである。それぞれの個体の背後にある普遍的なカテゴリー(プラトンが述べるところの「イデア」)こそが真実であり、観察される生物個体の多様性は、真実を近似したものでしかない(「洞窟の壁に映るイデアの影」)という見方である。
マイヤーによれば、チャールズ・ダーウィン以前の科学においてはこの類型学的思考が支配的であった。たとえば、ニュートン物理学においては物体の運動を規定する普遍的な法則があると想定される。個々の物体には、その法則からの予測とは外れた動きが観測されるものの、それはあくまで真なる値からの「誤差」であり、運動の本質的な特徴とは無関係なものと見なされるのである。
これに対して、ダーウィンが発展させたと評価されているのが、「集団科学的思考」である。この考え方では、それぞれの生物個体の違いには固有性があり、個体間のばらつきこそが現実を構成しているものだと捉えられる。
 図1 類型学的思考と集団科学的思考の対比(Mayr 2001を基に作成)
図1 類型学的思考と集団科学的思考の対比(Mayr 2001を基に作成)
類型学的思考においては時間・空間を超えた一般法則が探求されるのに対して、集団科学的思考においては、このような法則が存在するとは見なされない。そこで目的となるのは、時空間的に限定された概念に基づく現象の説明である。集団科学的な思考の下で、「自然選択」(natural selection)の概念を構築し、ダーウィンは生物の進化を説明することができたというのが、マイヤーの評価である。
社会科学の領域でも、このような集団科学思考は徐々に重要なものと見なされてきている。たとえば、社会学ではオーティス・ダンカンが様々な統計手法とともにこの思考の導入に大きな役割を果たし2、最近ではジョン・ゴールドソープもこうした立場を強調している3。
社会科学においては、決定論的な法則というものがあるとは考えられない4。社会を構成する個人はそれぞれの固有性を持っており、また社会現象の生起には確率的要素が含まれる。もちろん、確率的であるということは完全な偶然を意味するわけではない。ある社会現象の起こりやすさや、それが与える影響は人々の属性や地域によって異なり、経験的な規則性(empirical regularities)が観察される5。
社会現象には確率的な要素が含まれるために、物理学のように一般法則に基づいて現実を予測するようなことは困難である。むしろ求められるのは、ダーウィンが行ったように時空間的に限定された概念に基づき、観察される規則性に対してありうるメカニズムを提示し、説明を行うことである6。
2. 「危機対応の社会科学」における集団科学的思考の関連性
「危機対応の社会科学」において、上述した集団科学的思考はどのように関係するだろうか。まず、「危機」というものを「個人あるいは個人の集合であるところの国家・社会において、起こりうる望ましくないイベント」であると、ひとまず捉えてみよう。「危機」とは、起こるかもしれないし、起こらないかもしれない、すなわち確率的な現象であると考えられる。
もし、「危機」を必ず生起する決定論的なものとして捉えてしまったならば、それへの「対応」のあり方も著しく制限されてしまうだろう。危機対応学のリーダーである玄田有史教授が、「危険(リスク)を機会(チャンス)へ」という表現を用いている7ことにも、危機が起こるプロセスは確率的であり、それぞれの危機は可能性(chance)と捉えるべきであることが現れている。
「危機対応の社会科学」とはおそらく、危機の予測精度の高さによって評価される学問ではない。たしかに自然科学においては、災害などが起きる普遍的な法則を探求する分野が一部にはあるかもしれない。しかし、集団科学としての社会科学においては、「危機」とはミクロなものであれ、マクロなものであれ、その構成要素には固有のばらつきが存在するため、危機のプロセスとその影響評価や対応の方法についての、一般法則が存在すると見なすべきではない。
次に、より具体的な分析の面において、集団科学的な思考がもたらしうる長所について、若干述べたい。というのも、「危機」を含めて不確実性が伴い、自然科学的な法則をあてはめるだけでは答えが出ない現象に対する意思決定や対応策を探る学問分野としては、すでに科学技術社会論8などが存在している。こうした中で、新たに「危機対応の社会科学」を打ち出す意義については、より強調してゆく必要があるだろう。
集団科学としての社会科学が貢献しうる点としては、データ収集および分析の方法における体系性というものが一つ挙げられるかもしれない。集団に存在する固有の異質性を適切に記述し、また因果推論を可能にするための道具を、集団科学としての社会科学は発展させてきている。特に統計分析を用いた研究は、そうした異質性を捉えることに対して自覚的である9。
危機対応学プロジェクトにおいても、独自の質問紙調査がすでに実施されている10。集団科学的な思考に基づけば、マクロレベル(国家、地域、民族集団など)の現象の内部においても、ミクロレベル(個人)の大きな異質性が存在する11。こうした集団内の異質性を捉える上で、個々人から得られた統計データは不可欠である。たとえば、大きな災害を経験した一つの地域の内部においても、収入の高低や同居する家族の有無などによって、今後の起こりうる危機に対して行っている備えや、望ましい世の中についての意識には、個人レベルの大きなばらつきが見られるだろう。
以上のとおり本エッセイでは、社会科学における集団科学的思考の重要性と、それが「危機対応の社会科学」に対して持ちうる関連性について述べてきた。もちろんこうした視点に立たずとも有意義な研究は可能であろうし、あるいは集団科学的な思考に立ちつつも定性的な分析や歴史分析によるアプローチも可能だろうと思われる。しかし、このような思考のあり方を提示することで、そうではないアプローチとの有意味な対比であったり、危機対応学プロジェクトにおいてすでに行われている集団科学的な実践に対する明確性であったりを、わずかでももたらすことができたならば幸いである。