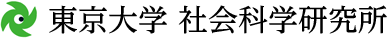研究
社研セミナー
日本における政治参加格差研究の現状と課題
境家史郎(社会科学研究所)
日時:2014年12月09日 14時50分-16時30分
場所:センター会議室(赤門総合研究棟5F)
報告要旨
ジャーナリズムにおいてもアカデミズムにおいても、選挙の際に話題となるのは、多くの場合、投票率全体の高低、すなわち「何人参加するか」(How many participate?)という問題についてである。昨今の選挙における投票率は、以前と比べて変化しているといえるのか。増加/減少しているとすればなぜなのか。他国と比べて、日本の選挙の投票率の水準はどのように評価されるのか、等々。こうした論点について分析を進めることは、社会的にも学術的にも、疑いなく重要なことである。
他方で今日、投票参加をめぐるもう一つの論点である、「誰が参加するか」(Who participates?)という問題については、しばしば等閑視されているという実態がある。選挙結果(および選挙後の選出エリートの行動)を左右するのは投票率の水準そのものではなく、むしろ投票者の構成(composition)であることを考えれば、”Who”問題は”How many”問題同様に、あるいはそれ以上に重要であると見なければならない。とりわけ、有権者の社会経済的地位(社会階層)と投票参加の関係がどのようなものであるかという点は、政治的平等性と社会的平等性の関係をめぐる、規範的にも重要な含意を持つ論点である。それにもかかわらず、「誰が参加するか」、あるいは投票参加の格差構造に関する実証研究は、日本では明らかに、またアメリカにおいても、近年までそれほど活発であったわけではない。以上の状況は、投票参加以外の政治参加行動(選挙運動や抗議活動への関与など)においても同様と考えてよい。
ところがごく最近になり、日米両国で、参加格差論が新たな展開を見せ始めている。2010年代に入り、アメリカで同テーマに関する、水準の高い研究書が相次いで刊行され(Schlozman, Verba, Brady 2012; Leighley and Nagler 2014)、日本でも新研究が現れ始めた(境家 2013; Matsubayashi 2014)。これらの研究は、いずれも政治参加格差構造の時期的推移(過去と現在の比較)について大きな関心事としている点が共通している。
本報告では、参加格差論の最近の研究動向について、その登場の背景を説明するとともに、簡単な新分析も交えつつ、内容上の要点を紹介する。また、日米両国における参加格差論の現状をふまえたうえで、日本の「政治参加と平等」研究が今後進むべき方向について考えてみることにしたい。