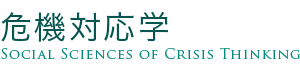第8章 グレゴリー・W・ノーブル「日本の『水素社会』言説―高リスクエネルギー政策と不安の利用」
(書評:橘川武郎)
橘川 武郎(きっかわ たけお)
国際大学大学院国際経営学研究科教授
2014年に閣議決定された第4次エネルギー基本計画は、水素について、「将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待される」と述べ、きわめて高い評価を与えた。これを受けて同じ14年に「水素・燃料電池戦略ロードマップ」がとりまとめられ、25年ごろまでのフェーズIでは燃料電池の社会的実装、20年代後半から30年ごろにかけてのフェーズIIでは水素発電の本格導入と水素供給インフラの確立、40年ごろへ向けたフェーズIIIではCCS(二酸化炭素[CO2]回収・貯留)や国内外の再生可能エネルギーと組み合わせたCO2フリー水素供給システムの確立が、それぞれめざされることになった。
このように14年を機に活発化した日本における水素社会への移行政策について、ノーブル論文は、事実と言説を検証したうえで、「水素が危機や自然災害の低減にきわめて重要な役割を果しうるという言説が強調される」(220頁)点に、欧米とは異なる日本の特徴を見出している。そして、水素をめぐって現時点で明白なのは、①「不確実性と危機の不安を利用して、早くても2040年代まで大きな成果が期待できそうにないハイリスク・ハイリターンの長期戦略が正当化されている」、②「危機に対する国民の不安につけ入って売り込んだ政策は、実質的な市民参加の余地をほとんど生み出していない」という、「二つの皮肉な事態の進展である」と結論づけている(222頁)。
日本の水素政策について国際的視点に立って鋭く切り込んだ好論文であり、国内の論壇では等閑視されてきた問題の本質に光を当てたノーブル氏の慧眼が光る。また、危機を利用した水素政策推進の中心勢力として「トヨタを筆頭とする自動車産業と経済産業省」(221頁)を挙げる点は、少なくとも現局面においては正鵠を射た指摘であり、政治学者としての筆者の面目躍如と言える。
このような基本的評価を確認したうえで、なお残るノーブル論文への注文を、2点ほど指摘したい。
第1は、水素政策の背景にある危機について、この論文では主としてエネルギー安定供給への不安に焦点を合わせているが、現実には、それだけでない要素も作用しているという点である。十分なリアリティがないにもかかわらず、日本の地方自治体やメディアの多くが水素への期待をふくらますのは、地球温暖化への危機感を急速に高めているからだと言える。従来のケースとは異なり、背景に、エネルギー安定供給への不安に加えて地球温暖化への危惧が加わっていることが、14年以降の「水素ブーム」の特徴と言えるのではあるまいか。
第2は、現時点で自動車産業が水素推進の主役となっていることは間違いないが、それは、あくまでロードマップが言うフェーズⅠに限定されるという点である。2030年における燃料電池車(FCV)80万台、家庭用燃料電池(エネファーム)530万台、というフェーズⅠの普及目標が達成されたとしても、同年の電源構成に占める水素の比率は2%程度、一次エネルギー構成に占める水素の比率は1%程度にとどまる。この規模では、とても「水素社会の到来」とは言えない。水素社会の到来のためには、大規模に水素を使用するフェーズⅡの水素発電の普及が必要不可欠なわけであるが、電力業界がきわめて消極的な姿勢をとっているため、肝心の水素発電への取組みはほとんど進んでいない。この事実こそが、日本の「水素社会」言説がリアリティをもたない最大の理由となっている。産業界と政府との関係の見取り図は、フェーズⅡまで視野に入れると、ノーブル論文のそれとは異なるものとなりそうである。