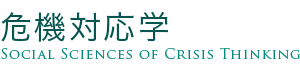第6章 藤谷武史「日本の財政危機を巡る事実と言説―なぜ議論が深まらないのか」
(書評:井手英策)
井手英策
慶應義塾大学経済学部教授
筆者の藤谷氏は、「財政危機」をめぐる文献を縦横無尽に渉猟し、「危機」の再定義を私たちにするどく迫る。氏が注目するのは、専門家による新たな財政・金融パラダイムをめぐる論争の中身ではない。財政と金融を一体化させ、その運営の全権を政府にゆだねんとする状況、別言すれば、統治の基本構造の転換すらせまられる状況のうちに「危機」をみいだし、国家と経済社会の基本構造の選択、その選択が生む不確実性や負担を引き受ける覚悟が市民の側に問われている、と主張する。
私は論争のさなかにある専門家であり、財政危機があたかも間近に迫っているかのごとき言説には批判的である。本稿にもあるように、日本銀行による財政ファイナンスが歴史的な政府債務の累積を可能にしてきた側面、家計の金融資産が潤沢であるだけでなく、企業の債務が減少し、これが政府債務に置き換えられ、全体で見た債務は制御されてきた事実、日本は世界最大の債権国であり、世界経済が不安定化すると「安全資産」である日本国債が買われ、円高がもたらされるという現実、これらに注目するからだ。
しかし、当面大丈夫であるということと、将来にわたって財政危機が訪れないということは同義ではない。また、財政が破綻しなければ何をやってもよいわけではなく、財政を民主的な統制の埒外におくかのごとき言説がまかり通る現状は問題である。藤谷氏の指摘する、正解らしく見える選択肢に飛びついて、あとはそれがうまくいくことを祈るという態度は、危機管理としては無責任でしかない。
以上の理由から、現代の危機を統治システムの危機として理解する氏の議論に同意する。とりわけ、危機と呼ばれた時代には、財政高権が通貨高権を支配するかたちで財政と金融の新たな関係構築が進み、両者の一体化が民主主義の形骸化と表裏だった経験を踏まえれば、なおさら氏の指摘は重みを増す。
一方、藤谷氏の財政危機の定義をめぐっていくつかの疑問がある。
氏は財政の危機を、社会や金融市場などの「危機(といった状況)」が「極めて急激なかたちで生じている状況」だという。「悪い結果が予測される危険な時、状況」(デジタル大辞泉)を危機とよぶのであれば、悪い結果が顕在化した状況は破綻ではないか。危機と破綻の混同は、「破綻しないから大丈夫、危機ではない」との安易な結論に結びつきうる。破綻しうる状況=危機だからこそ、予防すべきなのであり、そのことは藤谷氏の重視する統治システムの危機を克服するうえで重要な前提のはずである。
もう一点、社会や経済の危機が財政の危機をもたらす、逆の因果関係をどのように理解すべきか。藤谷氏は、日本で社会的な信頼度が低く、それが租税抵抗を生んでいる可能性を指摘している。また、勤労者世帯の所得の停滞は深刻で、家計貯蓄率の低下も顕著だという現実も無視できない。もし、社会的、経済的な危機が所得再分配への反発を強め、租税抵抗を生みだしているとすれば、財政危機は「結果」にかわる。J.シュンペーターは『租税国家の危機』のなかで財政危機を「兆候」とみなしたが、それは彼が社会の全般的な危機を映しだすものとして財政危機を捉えたからにほかならない。
本稿は筆者の博覧強記ぶりが遺憾なく発揮された力作だが、読後にモヤモヤした印象が残るのは、「財政危機」の定義が二通り存在しており、両者の関係が判然としないからかもしれない。だが、藤谷氏はこの問題を直感的に理解していたのではないか。というのも、財政危機が、その他の危機と相互に作用し合うからこそ、「一旦脇に置いたはず」のもうひとつの「捉え方」である民主主義の危機を反映した財政危機、すなわち、市民の立場からの危機の再定義へと議論の軸足がシフトしたように思われるからである。