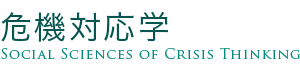第2章 石川博康「契約上の危機と事情変更の法理―債権法改正審議の帰趨とその諸文脈」
(書評:小粥太郎)
小粥太郎
一橋大学大学院法学研究科教授
1 石川博康教授の論考は、判例・学説に定着しているかに思われていた事情変更の法理--「契約締結後に急激な契約環境の変化が生じたことにより当初の契約内容での履行が困難となった場合において、契約の解消や契約内容の変更(契約改訂)などの法的効果を通じて、事情の変更によって不利益を被る当事者に対し一定の救済を与えるための法理」(32頁)--が、債権法改正(2017年)に際して明文化を見送られることになった過程を確認した上で、その要因を分析検討するものである。
2 債権法改正の前夜、民法学界においては、事情変更の法理に関する規定を民法中に新たに設けるべきであるとの意見が有力だった(五十嵐清「事情変更の原則の立法をどう考えるか」椿寿夫ほか編『民法改正を考える』272頁、債権法改正検討委員会編『詳解債権法改正の基本方針Ⅱ』381頁以下)。法制審議会の審議においても、当初から、その明文化という論点が提示されていた。ところが、審議の過程で、事情変更の法理に関するものを含め、学界からの重要な新提案は次々に姿を消し、学説側は、「連戦連敗」を喫したとされる(大村敦志『性法・大学・民法学』273頁)。事情変更の法理に関する規定の新設が見送られたことへの失望は、学界の各所にみることができるのである(吉政知広「事情変更の法理」安永正昭ほか監修『債権法改正と民法学Ⅱ』449頁以下参照)。
3 ところが石川教授の論考は、事情変更の法理につき民法中に規定を設けないこと(=民法学説の敗北?)の合理性を論証しようとするものとなっている点でインパクトがある。いわく、契約締結後の事情変更に起因する問題については、当事者による事後的対応が機能しているから(※1)、現在の法状況--事情変更の法理は抽象的には肯定されているが実際に最高裁レベルで発動されたことはない--以上に、法--最終的には裁判所--による他律的な解決規範を導入する必要はない(38-39頁)。また、事後的事情変更に対処するための再交渉プロセスは不安定であるから(※2)、事情変更の法理が明文化されるとこれを口実にした濫用、機会主義的行動が助長される(39-43頁)、といった具合である(実際の石川教授の論考は、※1、※2の事実が存在するなどとはせず、慎重に、それらの可能性に言及するにとどめている)。
4 このような--明文化見送りの--論証の仕方は、ときに民法学者が解釈論・立法論に際して規範的な正義ばかりを探究しているようにみえるのとは違って、「科学」的であるとの印象を与える。いうまでもなく「科学」は、規範的正義の探究に際しても重要である(太田勝造「基礎法研究者からみた『法と法学のエッセンス』」法時92巻1号16頁)。あえて批判を試みるなら、現在機能している当事者による事後的対応(※1)が規範的に積極評価に値するものであればともかく、そうでないなら、事情変更の法理の明文化見送りは、(強い立場にある契約当事者が)最高裁に引き続き沈黙を求める論理と変わらないものとなりかねない、あるいは、再交渉プロセスが不安定であり機会主義的行動による不当な利益獲得が抑制されるべきだとしても(※2)、主張そのものまで抑止すべきなのかどうかは疑問が残る、などといったものが考えられる。こうした角度からの反論を絞り出さざるをえないことになっている時点で、評者もすでに、石川教授の設定した土俵--ある種の実証的な議論の世界--に引き込まれつつあるということなのだろう。
5 石川教授の論考は、最終的には、個別契約における事情変更リスクにとどまらず、大規模な自然災害も念頭に置いて、契約法規範にとどまらず、国家の経済・社会秩序全体のなかでの事情変更の法理の役割にも論及する。その内容、とくに私法の領域にとどまらない国家法秩序全体を通じた多元的救済という観点(50頁)は、今後、事情変更の法理について考察する上でのみならず、危機と法律について考察する上でも示唆的である。