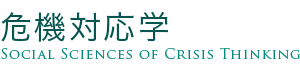第1章 林知更「憲法と危機―非常事態条項をめぐって」
(書評:片桐直人)
片桐直人
大阪大学大学院高等司法研究科准教授
著者の林知更によれば、「「危機」とは、一面では政治や経済といった社会的諸領域の現実のあり方の問題であると同時に......こうした様々な事象に「危機」を見出す人間側の思考の問題」であって、その意味で「「危機」とは一種の文化的事象」でもある。そして、危機に際して憲法論が語ろうとする様々なことも、この「文化的事象」としての側面を免れない。したがって、憲法論もまた、「「危機」の語りが我々に用意する落とし穴に陥る」危険性から逃れられない。
憲法における非常事態条項の挿入の可否という問題を巡ってしばしば目にする憲法論は、「各国憲法の比較研究」である。このような比較研究はその方法論的課題も指摘されて久しいけれども、今でもオーソドックスな憲法研究のスタイルであり、その目的とするところは、このような研究を通じて「モデル」を探るところにある。林もひとまずこれに依拠して各国の非常事態条項を検討するが、しかし、「我々が非常事態について考える際に依拠し模倣すべき標準的な規律モデル」は当然には存在しないという結論に至る。
そこで、林はより踏み込んで、「憲法が非常事態条項を持つことにどのような意味があるのか」を検討する。その際、考察の手掛かりとするのはドイツの憲法理論の歴史的展開であり、それを通じて、「何が問題だと認識されたのか」を論者のおかれた歴史的な文脈を踏まえつつ抽出し、その認識の変遷を追う。こうして得られるのは、たとえばカール・シュミットについていえば、ワイマール憲法48条解釈の前提となる独裁の議論(林の表現を借りれば「単なる国家諸機関の間の権限配分」)ではなく、非常事態条項と「法治国家の理念それ自体」の限界の緊張関係こそが問題の本質だという洞察であり、このような問題が戦後ドイツで継受されたからこその、ベッケンフェルデとリュッベ=ヴォルフの論争であるという分析である。このような非常事態条項の問題は法治国家の理念の限界問題であるという理解は、わが国においては――もちろん、幾人かの論者が指摘してきたものの――(メディアや政治の分野で繰り広げられるものも含む広義の)憲法論レベルでは十分に受容されていないようにも思われる。
しかし、林は、ここにとどまらず、さらに、本論文の最後で――いささか性急に――「法治国家の限界問題」それ自体も、そこまで重要な問題ではないのではないかという分析を付け加える。憲法論が危機を法治国家の限界問題として語ることを可能にするのは、「法治国家の厚み」を獲得しようと奮戦する日々のプラクティスの積み重ねであり、非常事態条項それ自体を議論するだけでは議論の進展は見込めない。そして、そのような日々のプラクティスは自然と危機を未然に法治国家的に処理することを可能にするということであろう。この点は、本論文ではじめて林の議論に触れる読者にはやや唐突に見えるかもしれない。しかし、このような理解は、林がこれまでの論考で繰り返し示してきたものであり、例えば林のモノグラフィ(林知更『現代憲法学の位相』(岩波書店、2016年))などを通じてその理論に親しんできた者にとっては、十分に理解可能だと思われる。
このように、林論文は、非常事態条項を巡る比較憲法史・憲法理論史的考察というスタンダードな手法に依拠しつつも、モデルの探求、権限分配の移動(ちなみに、憲法秩序を超えた権限分配の移動を可能にするためには、憲法秩序が前提とする国家の実体的認識=国家論が組み合わされることが多いが、林はこれまでこのような論理だての限界を繰り返し説いてきた)の可否や手法といったよくある議論を突き放し、さらには、法治国家の限界という議論さえ相対化して、日々の法治国家的プラクティスの彫琢を主張する。
評者もこのような林の主張に基本的に賛同する。非常事態においては(憲)法が窮屈であり限界があるというのは抽象的にはそうであろう。しかし、そのために具体的にどうしなければならないかを検討するには、法治国家のプラクシスが抱える課題を具体的にあぶり出すほかはない。そのためには、法治国家のプラクシスにあくまでも拘る姿勢こそが肝要であろう。
もっとも、そうだとすれば、返す刀で、次のような問題が突き付けられるかもしれないことは指摘しておきたい。震災にせよ、疫病にせよ、やはり危機と呼ばざるをえない「現実」はあるのであって、その際に展開される具体的なプラクシスもまた危機と無縁ではいられないのではないか。そうだとすると、危機を未然に防ぎうる法治国家のプラクシスは、やはり、平時のそれとは異なり、畢竟、「我々を不安にする危険な匂い」を法治国家の内部に漂わせることにならないか。今後、このレベルでの議論の披露も期待したい。