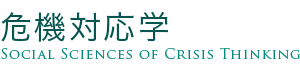第2章 ケネス・盛・マッケルウェイン「危機に対応できる憲法とは―安定性と適応性の間で」
(書評:宍戸常寿)
宍戸 常寿
東京大学教授
2020年4月、新型コロナウィルス感染症の拡大を防止するため、日本政府はいわゆるコロナ新法にもとづく緊急事態宣言を発令した。これに合わせて、緊急事態条項を憲法に設けるべきとする憲法改正の提案とそれに対する反論が、何度目かのブームを迎えている。
マッケルウェイン論文(以下、本論文という)は、こうした「改憲か護憲か」という日本特有の憲法論議の地平から距離を取る。比較憲法データベースを駆使して、世界各国の憲法における緊急事態条項の消息を探った上で、2012年自民党改憲草案における緊急事態条項の問題点を指摘するものであり、冷静で実のある憲法論議に貴重な貢献をした論攷である。
ごく単純に図式化して言えば、従来の日本における比較憲法研究は、英米仏独に代表される立憲主義国の歴史や文化に深く沈潜し、そこから共通の原理を探り解釈・運用の詳細を明らかにする、いわば「解釈論的」アプローチが主流であった。これに対して本論文の著者は、世界各国の憲法テクストの事項・内容を計量的に比較分析するアプローチを自覚的に採用し、従来の比較憲法研究には見られない数々の成果を生み出してきた。とりわけ、日本国憲法の規律密度が相対的に薄い(いわゆる簡潔・概略型の憲法である)ことを実証的に明らかにした作業は、現在の憲法論議における共通の前提にまでなっている。
本論文の第4節「世界の憲法における緊急事態条項」でも、そうした著者のアプローチが切れ味鋭く発揮されている。時代が下るにつれて各国憲法が「政治的に選ばれた人々に過大な権力を委任することに対して、ますます慎重になっている」こと(57頁)、「最も急ペースで規定率が上昇しているのは災害、とくに自然災害である」こと(58頁)、緊急事態が宣言・発動されるプロセスについて政府権限と議会関与の程度の相関(60頁)等は、いずれも、貴重な知見を提供するものといえよう。
本論文を超えて、緊急事態条項の意義について明らかにされるべき論点は多い。憲法テクストを重視する本論文のアプローチでは、緊急事態において憲法がどこまでを法律や行政命令に委ねているかが、指標としてクローズアップされる。しかし、憲法と法律と行政命令の区別の意義は、その国の憲法構造(大統領制かそうでないか、立法権が議会に排他的に専属する原則が取られているかどうか等)によって異なるのではないか。憲法テクスト上の差異から導かれる数値は、そうした憲法構造の比較とクロスさせれば、相対化される可能性がある。
また、憲法テクストを超える一国の法秩序のあり方も、緊急事態条項をめぐる問題の構図を左右するであろう。日本に即していえば、規律密度が薄いのは憲法に限られず、行政法規一般にも当てはまることではないのか。そのようなところで、こと緊急事態条項に限って、憲法テクストの規律密度を高めることは、現実には難しいように思われる。さらに、憲法及び法律の下で生じる執政の余地ないし行政の裁量について、議会や司法が平時にどこまでの統制機能を果たしているか、それらをどこまで国民が信頼しているかといった事情は、各国憲法における緊急事態条項の導入やその運用に対して影響を与えているかもしれない。
ここでこの種の論点を提起したのは、もちろん、本論文を非難する趣旨ではない。新たな問いを誘発し、あるいは問いを正確に定式化するための豊かな土壌を、本論文及びそのアプローチは提供している。解釈論的アプローチに立つ多くの憲法研究者にとって、緊急事態条項を有意味に論じるためにこそ、本論文は必読のものといえよう。
世間からも隣接分野からも、憲法とその研究のあり方に対して、厳しい視線が向けられることが多い。とりわけ「緊急事態」という、人々の生命や自由、国家の安全等に直結する問題については、「憲法守って国滅ぶ」というたぐいの主張を仮装するために、十分な検討なしで比較憲法由来の情報が呼び出されることが多い。いうまでもなく憲法は「不磨の大典」ではあり得ず、よりよき「政治の法」としてのあり方が不断に追求されるべきであるが、そのためには学際的・越境的な研究を含めた、多様なアプローチの多角的な協働が必要である。緊急事態条項の内容とトレンドの丁寧な分析を通じて、本論文はそのことを改めて読者に教えてくれているように思われる。