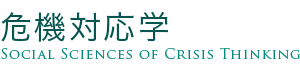第12章 藤原翔「教育、家族、危機―学校に対する評価の社会経済的差異とその帰結」
(書評:中村高康)
高学歴化は高卒学歴イメージを再帰的に修正するのか
―藤原翔「教育、家族、危機」(『危機対応学Ⅰ』第12章)を読んで―
中村高康
東京大学大学院教育学研究科教授
「危機対応学」。現代が様々な危機にとりまかれていることを理解するとき、たいへん魅力的なタイトルのシリーズである。ここに収められた藤原翔氏の論考を評するのが、ここでの私の役割である。
藤原論文がその論の下敷きとしているのは、社会階層論でこの20年来注目されてきたBreenとGoldthorpeの「相対的リスク回避説」である。この説は「子供が親の職業的地位と同程度かそれ以上になることを同程度に希望しており、職業的地位の下降移動の可能性が最小となるような教育選択を行うという仮説」(287頁)である。
この論考のもっとも重要な指摘は「不利な社会経済的背景にとって大卒が「遠い」というよりも、有利な社会経済的背景にとって高卒が「遠い」」(306頁)という事実である。確かに、氏の分析によれば、大学の便益を示す諸変数は、親の学歴の程度によっても変わらないが、高校の便益を示す諸変数では、高学歴の親ほど低くなる傾向を示している(図12‐2)。そして、高校の便益と大学の便益にギャップがあるほど、大学進学希望確率は上がる(表12‐2)。つまり、高学歴の親がいる家庭ほど高卒学歴が「遠く」、高卒学歴が「遠い」からこそ大学進学希望が増える、といったメカニズムが示されている。
従来の教育社会学的分析では、恵まれた階層の者や教育熱心な高学歴層で「大学」を望む傾向が強まるアスピレーション(野心)加熱と、逆に恵まれない社会層が「大学」を選ばないアスピレーション冷却が同時にイメージされ、それをもって格差が生じるメカニズムとして想定しがちであった。しかし、相対的リスク回避説では、恵まれた層の消極的な大学進学希望に着目する。これは従来の見方を補強できる有力な見方であり、藤原論文から相対的リスク回避説の魅力がとてもわかりやすくイメージできた。
ただ、私自身は学歴に対する人々の視線の変容を時代変化、とりわけ教育拡大ないし高学歴化と結び付けて考えている。大学に進学する人が増えれば増えるほど、学歴の神秘性は剥がされていき、大卒が大卒を否定しがちな状況が目立つようになる。これを後期近代という時代状況の中で生じる学歴の問い直し(メリトクラシーの再帰性)として提案してきた(拙著『暴走する能力主義』参照)。そうした見方を普段していただけに、この高卒への「遠さ」の指摘を読んで、これが高学歴化と連動した現象であるのか、あるいは時代変化とどうかかわるのかということがとても気になってきた。「大卒はたいしたものではないが、高卒よりは危機回避的に見える」、そんな学歴への問い直しのまなざしの台頭が時代的趨勢としてもあるような気がしてならない。これは、この論文の課題を超えてしまうが、そうした社会変動との関連も今後解明していただけると個人的には大変ありがたい。
私たちが認識する"危機"は、立ち位置によって違って見える。特に、社会的に恵まれない境遇に対して"危機"を強く感じるのは、実は当事者たちではなく、それよりも少し恵まれた位置に立った人たちなのかもしれない。断崖の上にいるときはそこが断崖だと気づかないが、離れたところから断崖の上に立っている人を見るとぞっとする、そんなメカニズム―それはもしかすると学歴の問題だけでなく様々な社会的問題についても同様かもしれない―が、この論考から透けて見えるのである。