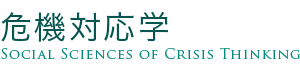第11章 中川淳司「アマチュア登山家の危機対応学―リーダーの要諦 」
(書評:國廣正)
國廣正
弁護士
この論考は、学生時代の北アルプス後立山連峰の冬山登山で、筆者(中川淳司氏)自身が体験した遭難寸前の危機的状況についての考察である。
評者は中川氏が所属していた東京大学の「法学部山の会」の同期生であり、現在、弁護士として企業の危機管理を専門にしていることから書評を依頼されることになった。
八人パーティーのリーダーであった中川氏が陥った危機的状況とは次のようなものだ。
➀鹿島槍ヶ岳を目指して稜線を進んでいたところ、猛烈な吹雪で進めなくなり、稜線上の窪地でのビバーク(緊急野営)を決断し、テントを張った(判断その1)。
②降雪(新雪)が激しく、テントに積もる雪で背中を押される状況になったので、当番を決め、就寝後は三〇分おきに雪かきをすることとした(判断その2)。
③しかし、一年生の雪かき当番が寝過ごしたためテントが大量の新雪で押しつぶされ、パーティー全員が窒息寸前の状況に追い込まれた(結果)。なお、押しつぶされたテントから辛うじて脱出できたので、中川氏はこの論考を書くことができている。
危機管理には、(1)生じうる危機的状況を事前に想定して、そのような状況に陥らないように準備すること、(2)危機的状況に陥った場合に、そこから迅速かつ適切に脱出すること、という二つの側面がある。
この観点から、中川氏のリーダーとしての危機管理対応を検証してみると、日程にも余裕を持たせて十分な装備・食料・燃料を準備していたこと、気象通報で天候を予想していたことなど、(1)の危機管理対応は適切に行われていたといえそうだ。
では、(2)の危機管理対応はどうだったか。
中川氏は、この点について、リーダーとしてミスが三つあったとしている。
一つ目のミスは、(判断1)にあり、稜線上の窪地ではなく、もっと安全な場所まで戻ってビバークすべきだったという。しかし、猛吹雪の中、さらに行動するのもリスクである。少し戻れば確実に安全な場所があるとは限らない。稜線上にテントを張れる場所はほとんどない。だとすると、窪地でのビバークはおかしな判断ではない。したがって、評者としては、中川氏の(判断1)にミスがあったとは思わない。
二つ目のミスは、(判断2)にあり、疲労していた一年生を雪かき当番にしたことだとする。しかし、これにも賛同できない。テントが雪に押しつぶされた原因は、「当番が寝過ごした」ことにある。寝過ごした当番がたまたま新人だったわけで、上級生でも寝過した可能性はある。
さらに、三つ目のミスとして、中川氏は、新人をメンバーに加えたこと自体がミスであり、そもそも新人(といっても一年間の十分な経験がある)を連れていくべきではなかったとまで言うが、これは「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」の類いである。リスクのある山にはどんなに有望でも新人であれば連れていかないというのでは、次の世代が育たない。
そうだとすると、中川氏のリーダーとしての判断にミスはなかったことになりそうだ。
ただ、そのように言い切るには疑問も残る。ミスがないのに、なぜ命の危険が生じてしまったのか。
危機管理論で重要なことは、危機を招いた原因の究明である。この場合に陥りがちなのは、危機の直接的原因となった事象(本件で言うと新人が寝過ごしたこと)を過大視することである。しかし、大切なことは「真因」の究明である。
本件での真因は、ビバーク場所は窪地で、雪が降り積もるだけでなく吹きだまりになってテントが押しつぶされるという「命の危険」があるということまでは「想定」していなかった点にあるのではないか。雪かきの必要性までは認識していたことは明らかだが、もし、命の危険まで想定していれば、寝過ごすリスクの重大性を考えて雪かき当番を二人一組にするとか、寝ずの番を立てるなどの対応が行われたと考えられるからである。この意味で、危機を招いた真因は、危機(命の危険)の想定が不十分だったことにあると思われる。
仮に評者がリーダーであったとしても、おそらく中川氏と同じ判断をしたのではないかと思う。しかし、人類にとって最高の知恵は「後知恵」である。この論考及び「後知恵」により評価する評者の考察は、危機管理の核心は「想定力」にあることを示しているといえるのではないかと思われる。