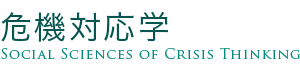第1章 宇野重規「政治思想史における危機対応―古代ギリシャから現代へ」
(書評:猪木武徳)
猪木武徳
大阪大学名誉教授
宇野重規氏の論文は、「危機対応」を論じたラインハルト・コゼレックとカール・シュミットの論を取り上げて明晰かつ広がりのある検討を加えている。問題の所在が手際よくまとめられており、その力量に感心しつつ読み終えることができた。論文の視座・要約は冒頭に簡潔に記されているので、ここでは宇野氏の今後の更なる研究に期待しつつ、望蜀を承知の感想を記すことで責めを塞ぎたい。
危機の問題は、西洋思想、特にユダヤ・キリスト教思想ではその中心的な位置を占めてきたと言っても言い過ぎにはならない。「終わりは近づいているが、まだなされるべき決定は行われていない」という確信が、人々に共有されたときに危機が訪れる、とのコゼレックの考えは、イエスの新約思想の出現と重なるところがある。これはユダヤ・キリスト教の中の「革命思想」と同形のものだとも理解できる。史的イエスは、律法学士とパリサイ人の旧態依然たる律法による秩序形成を否定し、「愛せよ」という新しい法を社会に持ち込んだ。つまり旧法の形式的支配で危機に瀕していた社会に、新しい法を持ち込んだわけであるから、イエスは「革命家」なのである。
宇野氏の論考は、「古代ギリシャから現代へ」と副題が付されており、危機とそれへの対応に関するキリスト教神学の理論への言及はない。シュミット(カトリック系)とほぼ同時代のプロテスタント神学者 K. バルトの理論(「危機神学」「弁証法神学」などと呼ばれた)に見るべき論点はあったのかなどは、評者には未知の分野であるがゆえか関心が湧くところである。
危機と批判の結びつき(例えば批判が危機をもたらすという可能性)を問題の鍵とする宇野氏の指摘は納得できる。宗教改革によって、信仰は人々を結びつける紐帯ではなくなり、むしろ人々を分裂させる原因となった。その結果、個人の良心を国家から切り離し、政治と道徳の分離を目指すことになる。(宇野論文p.35)政治と道徳の分離を「決定づけた」というのは確かであるが、「個人の良心」と「社会の秩序」の葛藤は、古代ギリシャ社会でも政治と道徳をめぐる最大のアポリアであったのではないか。ギリシャ悲劇のテーマのひとつは「よき個人、必ずしも良き市民に非ず」という難問である。(『アンティゴネ』のクレオンはその顕著な例であろう。)
宇野氏はこの論考で、シュミットの理論を分かりやすく整理している。事前の規定と事後の検証の問題、いかなる状態を危機と同定するのか、そしてその危機を誰が判断するのかという難問。これらの論点はいずれも「法の概念」にまでさかのぼって検討されねばならない政治思想の難所であることは言うまでもない。
最後に蛇足めいたコメントを二つ付け加えておきたい。本論文で宇野氏が解説する独裁、僭主、専制などの政治学の基礎用語の区別を、日本の論壇やメディアに関わるものは時局を論ずるとき知っておくべきだということ。もうひとつは、評者が見てきた経済の生産職場や企業組織における「例外状態」にも、誰が、どのように判断するかという重要問題が存在するということ。したがって経済組織といった視点からも本論文は興味深く読める。経済活動という日常行為(ordinary business)においても、(危機とは言わないまでも)異常や変化は必ず起こる。かつてフランスや東南アジアの工場調査を行って、この「異常と変化への対応」能力が、工場や企業全体の生産性を強く規定していることが分かった。そのように読み替えると、宇野論文の高い実践性を具体的に理解することができる。