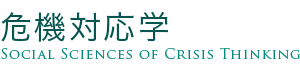「危機対応学」開始にあたって
全所的プロジェクト運営委員会
危機対応学は、社会に発生する様々な危機について、そのメカニズムと対応策を社会科学の観点から考察する新たな学問である。それは2016年度からの4年間を研究期間に、東京大学社会科学研究所の全体を挙げての全所的プロジェクトである。所内公式名称は「危機対応の社会科学」という。
一般にリスク(危険)が望ましくない状態を構成する要素だとすれば、クライシス(危機)とは望ましくない状態そのものであり、さらにはその状態への分岐を意味することもある。危機とは「危険」な状態であると同時に、対処によっては新たな「機会」を生み出す契機ともなる。リスクがその発生を管理されるべき対象とすれば、対応のあり方によって様々な産物や副産物を生み出すのが危機である。
リスク管理論は、リスクの最適管理方法を論じるところに意義がある。それに対して危機対応学は、危機への対応に向けた方法とその帰結を、社会に生きる人々が広く認知し、なかでも危機によって影響される人々への周知が行き届いた上で、適切に履行するための条件や環境に着目する。危機対応学は、危機を危機として認識し、行動することを可能とする社会状況について考察する社会科学研究である。
危機への対応を考察し、なおかつ広く多くの人々との共有や実践をはかるには、確かな視点となる「軸」の設定が求められる。その一つが危機対応に関する時間軸である。時間軸は、危機が発生した時点およびその後に、その危機にいかに適切に対応していくかという事後的対応のフェイズと、潜在的な危機の可能性を予め認知し、適切に対応しようという事前的対応のフェイズの両者から構成される。
うち事後的対応に関しては、前もって想定されてきた危機が発生した場合の対応のみならず、予見が不可能だったり、認識の共有がなかった「未知の危機」が想定外に生じた際の対応や処理方法が、切に問われることとなる。危機は統制することで克服できる場合もあるが、管理自体が困難な場合も少なくない。統制や管理を凌駕する危機が発生した場合に、危機を同時代的に受容しつつも、被害を最小限に食い止めるための手立てとは何かを、危機対応学は追究する。
他方で、事前的対応に関しては、危機の可能性に対する事前的な認知と準備を促進もしくは阻害する「社会的な力学」について、社会科学的な観点から考察していく。危機が社会に襲いかかったときの状況のイメージを逞しくし、冷静かつ万全な対応をはかるには、前もって何をすべきなのか。危機対応学では、あるべき事前対応策の具体像の把握を目指す。
危機の未然防止には、潜在的な危機への自覚を日常的に持ち続けることが求められる。だが蓋然性の高い危機でも、人々がそれに抱く「危機感」もしくは「危機意識」は一般に乏しいことも少なくない。反対に、蓋然性が低い危機に対して、強い危機意識が醸成される場合もある。科学的な危機確率と社会的な危機意識の乖離を生む要因を把握することも、危機対応学の目的となる。
以上の時間軸に加え、危機対応学では、対応の担い手としての主体のレベルに関して、もう一つの考察軸を設定する。具体的には、個人、国民、市民、住民等といった個々を主体としたミクロ的対応の側面と、集団、国家、コミュニティ、地域等の総体を想定したマクロ的対応の側面を、論点の明確化に向けて区別しつつ、考察を進めていく。
ミクロ的対応に関しては、個々人が、その経験や知識に基づき、適切な危機対応力を発揮できる社会条件を明らかにする。そこでは個人を取り巻く社会環境として、危機対応に取り組むための、学習や誘因、情報の獲得機会などに目を向けていく。その上で個々の判断や行動に基づくミクロ的危機対応が、ひいては普遍的な危機対応策として定着することが望まれる。そのための民主的なルールや手続きは、いかにして構築可能かにも危機対応学は焦点を当てる。
マクロ的対応に関していえば、危機からの被害を最小限に抑えるべく、国家等による統制や権限が認められる場合も少なくない。その一方で、危機という言説の濫用が、ときに社会全体に及ぼす負の影響にも留意していく。危機を必要以上に強調する国家や集団等における言説と振る舞いが、結果的に権力の横暴を許すことにつながったり、国民の判断を歪める場合も懸念される。国家が介入・統制すべき危機もあれば、国民自身の手に解決を委ねるべき危機もある。だとすれば、その両者はいかに適切に峻別すべきか、さらにはそもそも峻別自体が可能であるかも、危機対応学では問われることになる。
ミクロとマクロの視点は、論点の明確化を促すと同時に、危機に関する個と総体との相乗効果の考察も可能とする。一例として、国際的にみて、他者に対する信頼性が乏しいという現代日本人のミクロ的特徴が事実とすれば、個々人相互の不信や信頼欠如が、現在および将来にわたって、どのようなマクロ的危機をもたらしているのだろうか。
反対に、何らかのマクロ的な危機対応のあり方が、個々人から他者に対する信頼を奪い、ミクロ的危機対応を困難にしている面もあるかもしれない。だとすれば、そこにはどのようなプロセスが働いているのだろうか。危機対応には、社会における信頼の醸成が不可欠だが、そのためにはミクロ的危機とマクロ的危機の対応関係が明らかにされなければならない。
危機対応学が、その公式名称として、危機対応の社会科学と銘打ったのにも理由がある。
危機には人知を超えて自然発生的に起因する場合もあるが、人と人との関係により作り出される「社会が生み出す危機」も無視できない。だからこそ、危機対応の研究には、自然科学的な考察とならんで、社会構造や社会関係を研究対象とした、社会科学的な考察が不可欠となる。
社会科学の目的の一つは、社会における因果関係の解明にある。危機の原因と帰結の関係を見誤ったとき、いかなる惨事が社会に生じるのか。たとえば財政危機が深刻な社会の危機の帰結であると捉えたとき、その背後にある本質的な危機は、社会の状況が財政に及ぼす因果関係の解明によって、はじめて発見可能となる。
また想定外で未知の危機は、正確な把握が困難な場合であっても、対処への想像力を高めたり、なんらかの手立てを備えておくことは重要である。そのためのヒントは、未来予測とはむしろ反対に、過去の歴史に目を向けることで見つかる可能性も少なくない。
社会科学のなかの歴史研究には、戦争、恐慌、災害など、過去に生じた様々な危機の原因と影響を考察した知見や知恵の蓄積がある。第一次世界大戦など、誰もが望まず、想定すらしなかったにもかかわらず、危機対応を誤ったために、深刻な大惨事を招いた歴史の典型である。歴史的考察から得られる教訓は、今後の危機対応を考える上で、必ずや多くの示唆を提示してくれるだろう。
社会における法や制度は、そのほとんどが何らかの意味での危機対応を目的として含んでいるともいえる。法学、政治学、経済学、社会学などの社会科学は、法や制度が社会に与える影響を、それぞれ独自の観点から考察してきた。
法や制度の持つ意味や利用のあり方は、時代とともに変化する。リスクの複雑化が進む社会状況のなか、法の発動や制度活用の頻度が増すこと自体、危機を抑止するというよりは、むしろ危機そのものを増幅させてきた面もある。危機に対する法や制度の役割を、的確かつ多面的に考察するには、既存の学問分野の垣根を超え、社会科学を総合する取り組みが欠かせない。
以上の問題意識を踏まえ、文献資料の検証、量的・質的な調査分析、特定地域の実地調査などを組み合わせつつ、発足から70年間に培われた学際性と国際性という、東京大学社会科学研究所の特徴と実績を活かした総合研究として、危機対応学を進めていくこととする。