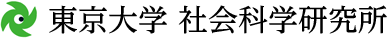案内
外部評価報告書
個別報告書
石井 紫郎
東京大学社会科学研究所 外部評価報告書
2000年2月22日
1 はじめに
東京大学社会科学研究所(以下、「社研」という。)が、今回いわゆる外部評価を受けようとするのに際し、その目的、コンセプト、実施スキーム等について内部で十分議論をつめ、それに基づいて明快な「自己点検・自己評価報告書」を作成して、関係資料とともに、実地視察ないしヒヤリングに先立つこと十分な時間をもって評価委員に送付したことを、まず高く評価したい。これは本来当然のことではあるが、一般には必ずしも実行されているわけではないので、特記する次第である。
また、外国人研究者を評価委員に委嘱するに当たっては、社研の客員教授として招聘されたことのある者を除く方針を採ったことも、他の教育研究機関が範とすべきこととして特記しておきたい。
2 研究体制・研究活動について
1)社研の中心的課題について
まず、最近の社研がその研究活動の中心的課題として日本社会研究を掲げ、それに適合的な人事構成を図る、という基本方針について一言するならば、この(日本社会研究という)結論に異論はないが、その根拠が些か薄弱ではないか。主として国際社会における日本のプレゼンスの高まりがこの背景にあるようだが、だとすれば中国のプレゼンスが大きくなれば、そちらへシフトする、という性質のものなのであろうか。
思うに、ある社会科学の組織・機関が全体として何を中心的課題とすべきか、についてはさまざまな考え方がありえようが、社研の場合、主観的な自己認識はどうであったかは別として、横から見ていると、創設以来ほとんど常に日本社会研究がその中心的課題であったのではないか、という印象を抱くのである。
もちろん、制度的にも実際の人的構成の面でも日本研究が中心となっていたわけではない。むしろ外国研究部門・研究者の比重は法学部・経済学部に比して明らかに大きかったが、「全体研究」の時代から、「戦後改革」は無論のこと、「基本的人権」であれ「ファシズム期の国家と社会」であれ、それぞれのテーマについて、日本を一般理論の枠組みの中で、あるいは「比較」の視角から分析しようというスタンスはほぼ一貫していたのではないか。日本に論及しない理論研究や外国研究が、個々的には含まれてはいても、一つのプロジェクトとしての一体性を与えるものがあったとすれば、それは「日本」だったのではないか。
私は、このようなスタンスは「全体研究」・「全所的プロジェクト」として、健全であり、ある意味で、そうでしかありえないものと考えている。おそらく初期は「一般理論」の枠組みへの思い入れが強かったため、「日本」がそれほど強く意識されなかったに過ぎないのではなかろうか、とさえ思っている。
2)人事構成について
初期社研の部門制が「日本研究シフト」を敷いていたわけではないことは、上にも述べた通りであり、その時代の人事が今に与えている結果が、昨今の「自覚化された日本研究シフト」とややそぐわない印象を与えていることは否定できないかも知れない。しかし、これも上述したように、理論研究、外国研究は「日本研究シフト」にとって本来重要な要素であり、人事構成の現状が直ちに「後遺症」と見做されるべきものではない。
それに加えて、国際化の進行は日本を「個体」として観察するだけでなく、「関係」において観察することを必然化するのだから、狭い意味での日本研究者(日本しかやらない「日本屋」)は不要化しつつある。
それ故、人事構成で心がけるべきは、「日本研究シフト」に合わせて「日本屋」を多く採るのではなく、逆に専門的にも、国籍の上でも「国際化」することである。その点、最近の人事の成果は、専門の面では十分評価されてよいが、国籍面で問題を残している。
3)人事方式について
いわゆる後任人事方式をやめ、研究組織委員会が中期的展望に立ちつつ「所の研究活動全体を見渡して最適な人事選考分野を提案する」という方式を採ったことは高く評価される。ただ、実際問題となると、この方式は非常な困難を伴う。私の勤務先はそもそも部門制を一切採っておらず、いわば始めからこうした人事方式を採ってきたところであるが、その経験からいって、実際にはこれは非常に難しいものであることを認めざるをえない。社研が掲げる「新分野の開拓」、「人材本位」、「基幹的分野の確保」という3つの要請(「自己点検・自己評価報告書23ページ)は、自分の身にも覚えがあるが、相互に矛盾しあう面をもっている。しかし、方式としてはこれが最善であることは間違いないのだから、これで努力するしかない。スタッフが持ち合わせる情報には限りがあるだけに、公募(海外を含む)制を導入するべきではないか、という考え方に個人的には傾きつつある。社研はこの点どうなのだろうか。
教授の業績について外部評価を導入したことも高く評価される。しかも、所全体の外部評価と切り離したことも理にかなったことと思われる。一般に、組織・機関の評価と個人の業績評価を一緒くたに考える傾向があるが、両者の違いをはっきり意識し、評価体制、評価者等についてそれぞれに相応しいものを工夫する必要がある。この点、社研のやり方は適切である。
4)全所的プロジェクトについて
これまでの研究成果については、批判や注文もあろうが、私は、とにもかくにも社研が6つのプロジェクトの成果を世に送り出してきたことの意義に注目したい。上述したように、これらは一貫して「日本研究」であるというのが私見であるが、まさにこの持続性が重要である。社研という一つの機関が、切り口や問題設定はさまざまではあれ、30年間日本の社会科学的研究を実施し、成果を生み出してきたということは、一種の日本の「定点観測」ともいうべき意味をもつと言えるのではないか。「教科書的」・「総花的」と評価する向きもあるが、それは、「定点観測」としてなら、むしろメリットかも知れない。
むろん、「定点」は「不動点」ではない。そもそもこの宇宙に「不動」の点などありよう筈もない。動きつつ、しかも同一性を失わない「点」が日本を観測し続けたという、その軌跡は、それ自身、日本と日本の社会科学を知るための貴重なデータである。
ただ、これまでのテーマ選定の手続や運営体制が万全であったかどうかについては、事情に暗い者として、判断を留保するしかない。参加者間のモティヴェイションの温度差はやや気になるところである。
その点、今後テーマ選定に当たっては、十分な議論が積み重ねられ、全参加者が十分な意欲をもってプロジェクトが実施されるような配慮が必要であろう。複数プロジェクトの連携構造の「重層的展開型」を目指すことは、この点で有益であろう。
テーマについては、所の基本方針たる日本中心は当然として、とくに社会と科学技術の関係(STS:Science and Technology Studies; Science,Technology and Society)を視点の一つに加えてほしいものである。
なお、今後は一つのプロジェクトの実施期間を少し延長することも考慮してみてはどうか。多様性を許容する「重層的展開型」を構想するなら、期間延長の必要性も増大するであろうし、科研費等のプロジェクトがほとんど5年以下、という状況に鑑みると、社研の「全所的プロジェクト」なればこそ、というじっくり腰を落ち着けたものを構想する余地もあるのではないか。
3 国際活動について
客員研究員・研修員の受け入れ自体は珍しいものではないが、その数と顔触れを見ると尋常ではない。こうして培われた人脈は社研の貴重な「財産」であり、今後の「全所的プログラム」の国際化等に大きな役割を果たすであろう。
客員教授ポストは、比較的短期の招聘期間で回転を早くする(人数を多くする)運用がなされているようであるが、それは意図的なのか、結果としてそうなっているのか。どのくらいの招聘期間が適当かは、むろん一律には決められない問題であるが、もし共同研究や全所的プロジェクトとの関わりを重視すれば、もう少し長期の招聘も考えてみる必要もありはしないか。もっとも、ポストの数が限られている以上、それにも限界があろうが。
総じて、このような人的国際交流については、社研が「日本研究シフト」を敷く以上、文部省その他に対してもっと強力に働き掛け、さまざまな点での改善を図っていくべきである。むろん「これまでさんざん努力しました」とお答えになるだろうが、「横並び」を警戒する日本の官僚制を相手に予算要求するには、「特殊性」の主張・説明が必要であって、その点の工夫の余地はまだあるのではないか。
交流用のスペースの質的・量的貧困は目を覆いたくなる。経済学部横に経済学部、教育学部等との共用棟の建設が進行中であるが、その計画に当たって、社研用の面積の積み上げ根拠として「国際交流」分をどのように要求したのだろうか。
大学や学部・研究科・研究所は「個性化」を求められている。それを、大学サイドの努力で予算の「横並び」主義打破に結び付けようではないか。高等教育・学術研究の国家予算をGDPの 0.5%から1%へ増加させよう、という要求は、おそらく大学側がさまざまな「個性的要求」を説得力をもって具体的に打ち出していくことによって、現実化の道が開けてくるのではないか。ただ抽象的に「2倍!」というだけでは、布団屋のコマーシャルと変わらない。
英文雑誌SSJJをレフェリー制の国際水準のものとして刊行しはじめたことは高く評価したい。海外からの評価が高いのも当然であろう。問題は、これを持続させることである。コンテンツに関する編集体制をより確立させ、社研のスタッフに過重な負担がかからないようにしないと、長続きはむづかしい。この点でも「日本研究シフト」に基づく「個性的」要求を工夫すべきである。これと並んでSSJ-Forumも国際的に評価されているプログラムであるが、これを発展・定着させるための方策についても、行政当局に強くアピールしていくべきである。
4 教育参加について
教育は研究に多大の刺激を与えるものであり、その意味で研究所の教官も教育に参加すべきだ、というのが私見である。むろん、どのレベルの教育に、どの程度参加すべきか、は研究所の目的・使命との関係で慎重に決められるべきことであるが、「研究だけしていればよい、という幸せなご身分」を強調し過ぎるのは問題である。
ただ、他大学の非常勤講師としての講義は、私見によれば、自己の学問の体系化の契機になるという点を除いて、あまりメリットはない。やはり、その教育に、機関の一員として責任を負っている相手に対する教育(社研の場合でいえば、法学政治学又は経済学研究科の学生への教育)は、自分自身を裨益する。本場所と花相撲の違い、というと語弊があるかも知れないが・・・・。その点、社研が、教官の他大学への出講を週2コマに制限して、本務へのコンセントレーションを大切にしているのは、立派な見識である。
なお、以上の一般論に反するようだが、教養学部のフレッシュマン相手の演習は、相手のためにも、自分のためにも非常に有益であるので、現在以上に参加することも検討されてよいのではないか。「鉄は熱いうちに打て」を実感するのはもちろんだが、「熱い鉄」を(1学期の間)打っている「手応え」は貴重な体験である。「熱いうちに打」たれた鉄は研究者志望の率が際立って高い、ということも付け加えておこう。
独自の研究科の設置を追求することは、一般論としては、悪いことではない筈である。ただ、東大内の他の研究所との連携によって、バランスのとれた研究科が出来るか、その中で社研が無理なく「専攻」として位置付けられるものになるか、という点について慎重な見極めを必要としよう。社研自体の将来構想をこの研究科設置が逆に縛るようでは本末転倒であろうし、また修士課程から独自のものをもつか、(後期)博士課程からのものとするか、も重要な論点である。私の勤務先は後者の形を採っているが、研究所としての性格と適合的な面をもつ合理的な形態だという実感をもっている。とはいえ、ロースクール構想、ビジネススクール構想等が渦巻いている中で、法学部、経済学部と密接な関係にある社研として、この選択には慎重な見極めが必要であろう。
要は、「なんとか自前の大学院を」という執念に駆られることなく、冷徹に利害得失とフィージビリティーを測定することである。その点「研究所の研究活動の成果をより一体的に反映するため」という(自前の大学院を求める)理由付けには若干問題を感じる。学際的な「日本社会研究」の大学院教育に関する、国際的に魅力あるカリキュラムの構想こそが決め手ではあるまいか。
5 日本社会研究情報センターについて
データ・アーカイブの充実は今後の社研にとって最重要課題の一つとして位置付けられるべきものであろう。天文学にとって大型望遠鏡、素粒子科学にとって大型加速器が不可欠であるように、これからの社会科学にとってデータベースの整備は不可欠である。
翻って日本のデータベース構築の予算は、科研費の「研究成果公開促進費(データベース)」中心という状態で、データベースは、個々の具体的な研究の副産物程度にしか扱われていない。その点でも、「日本研究シフト」の「個性的要求」として、データベース構築そのものを固有の事業として取り組むことの必要性・有用性を訴える努力が必要であろう。
なお、日本のデータベースは一般的に使い易さという点で弱点をもつものが多い。これは上述の「研究の副産物」という扱いとも関連することで、おそらく作成者(の方法論や問題関心)の個性・癖が作用しているためではないか、と憶測しているところであるが、社研の情報センターの事業としては、個々のデータベースの構築とともに、日本社会研究のためのデータベースのあり方についてモデルを提示することまでも視野に入れてほしいものである。
6 助手制度について
研究助手制の運用を「全所的プロジェクト」をはじめ、「研究所全体の研究体制にインヴォルブする」形に変えることについては、結果を見守りたい。ことに「全所的プロジェクト」等について公示して募集することになると、実際には(潜在的)能力よりも課題への適合性を重視した採用が行なわれ、また応募側もそれを意識して応募者に偏りが出てくるという恐れもあるのではないか。
また、新しい運用方式は、論理的には、法政系の「修士取得者」採用というこれまでの原則に修正を迫る要素をもっているのではないか、等、「やってみなければわからない」というのが実感である。
助手というポストは汎用性をもつ、便利なものだけに、むづかしい問題である。研究者養成に欠かせない、と腹を括って学部卒を採り続けている東大・京大法学部でも、細かい手直しは常に行なわれているといってよい。試行錯誤は助手制度が存続する間(以外に短命かも知れないが)続くと考えておかなければならないであろう。
7 終わりに
最後に、あらためて強調したい:だれが見ても施設があまりに貧困である。国際交流の項で指摘したが、この問題はすべての面で強調しなければならない。もちろんこれは、社研だけの問題ではないし、根本的には社研に責任を帰すべき事柄でもない。上述した建設進行中の共用棟の完成で改善されることを期待したいが、抜本的な改善になるとは、他の例から見て、到底考えられない。結局、「ガマン、ガマン」状態は続くであろう。
さしあたっての問題は、その(不十分な)拡大するスペースを何に振り向けるか、であろう。所内ではすでに計画は立てられているであろうが、「等しからざるを憂う」主義でいくと、社研の「日本研究シフト」と齟齬を来すことも考えられる。思い切って「国際主義」、あけすけにいえば、「外面(そとづら)重点主義」に撤することはできないものであろうか。海外からの客員研究員・研修員に現状より格段に良好なスペースを与え、図書館部分に快適な閲覧部分(キャレルでもよい)を設ける、等々、将来への投資(社研ファン・応援団の育成)だと思って、身内は我慢するくらいの決意でないと、改善を実感することにはならないであろう。法学部が教官中心主義のスペース配分方針を採り続け、結果として永続的・多角的な国際的連携の点で問題を来しているかに見えるのを他山の石とすべきである。
しかし、このような「やりくり生活」を強いられていることに、大学人はもっと憤りを抱き、外へ向かって発信すべきである。国立研究機関が全てかくも貧しいかといえば、必ずしもそうではない。「横並び」主義が99国立大学に適用されていることの意味は無視できないように思われる。「個性化」・「特化」と高い成果を上げることで「横一線」を抜け出す--このことは、独立行政法人化しようとしまいと、日本の高等教育・学術研究機関の生き残りのために不可欠なのではなかろうか。