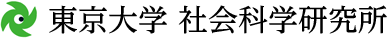案内
東京大学社会科学研究所の現状と課題
外部評価報告書 座長のまとめ
東京大学社会科学研究所 外部評価報告書
2000年2月22日
東京大学社会科学研究所 外部評価委員会
ジェラルド・L・カーチス
(座長)石井紫郎
金 泳鎬
北川 善太郎
マリ・サコー
高畠 通敏
寺西 重郎
吉川 弘之
【以上、アルファベット順】
1 はじめに
本委員会は、東京大学社会科学研究所(以下、「社研」という。)の依頼を受け、その研究、国際協力、教育等の諸側面に関する組織のあり方や活動状況の評価を行ったので、ここに委員会としての報告書を取りまとめた次第である。
本委員会は、社研から予め送られた「自己点検・自己評価報告書」と関連諸資料を査読した後、1999年11月19日に社研を訪問して視察とヒヤリングを行い、引き続き合議を行った結果、各委員が個別に評価報告書を作成することとした。なお、日程の都合等でこれに参加できなかった委員も若干あったが、各自別の日程で視察・ヒヤリングの機会をもった上での報告書であることはいうまでもない。
委員会報告書は、上述の合議の際の了解に従い、次のような方針で作成されたものである。すなわち、評価は客観的なデータの公平な分析に基づいて行われるべきものであることは当然であるが、究極的には各評価者の主観から自由ではありえないものであり、また無理に統一的な見解に融解させるよりは、多元的・多角的な諸評価をそのまま提示した方が、社研の自己改革・改善に資するところが大きいであろう、という判断から、委員会報告書の本体は各評価委員の個別報告書の集合体とした上で、それらに通底する論点を座長の責任においていくつか提示することによって、報告書のカヴァーページとするものである。
なお、社研側からは特に評価を受けたい諸項目が提示されていたが、各評価委員がその全てについて明示的に応えたわけではなく、その意味で、以下の叙述は全ての個別報告書に共通する意見の摘出ではないことを断っておく。
2 研究体制・研究活動について
社研が「日本社会研究」を研究活動の中心的課題に掲げることについては、(理由はさまざまではあるが、)概ね肯定的な評価を受けたといってよい。問題は、このスタンスがどの程度恒常的なものか、という点にある。それは、この課題設定の動機ないし理由付けとも絡む事柄であり、《(設置目的が外国研究にない)一つの社会科学研究機関が組織として掲げる課題は究極的には自国研究に帰着せざるをえない》という理由からなら、このスタンスはかなり恒常的なものになるだろう。国際社会の日本への関心の高まりがその理由なら、このスタンスの寿命はそれほど永続的なものにはなりそうもない。ある評価委員がいうとおり、少なくとも「日本社会研究そのものがかってのような華々しさを失いつつあるなかで、どのような意義をもちうるかについえては絶えず厳しい理論的実践的吟味」を続けていかなければならないであろう。
また「日本社会研究」という基本的スタンスに(無意識にせよ)「脱亜入欧」的傾向がありはしないか、という指摘は、日本人同士では気が付きにくい問題であるだけに、謙虚に耳を傾けるべきものであろう。
いわゆる全所的プロジェクトについては、少数を除いて、概ね積極的な評価を受けたといってよかろう。ことに30年間に渉り、そのときどきの重要課題について、所員の大部分が参加する研究活動が持続してきたことに対して、高い評価が与えられた。しかしその内容・成果については評価が分かれたといってよい。
テーマ選定のプロセスにおいてボトムアップの原理がどこまで働いていたか、それと関連して、参加者の意欲に温度差が見られるのではないか、といった点については、かなり厳しい意見が寄せられている。そして、このことと、研究成果に見られる物足りなさとが連動しているのではないか、という指摘は、今後の社研にとって重要な論点であろう。
このプロセスの問題は、一評価委員から出された「全所的プロジェクトというコンセプトそのもの」に対する原理的な批判とも、深く関わっているのではないか。この批判は、極端にいえば内発的な関心が薄い者をも「所員」だからといって巻き込んでいく(ように見える)全所的プロジェクトに対して、アングロサクソン的思考が拒絶反応を示したものと思われ、一見孤立した意見のごとく見えるが、実は、テーマ選定のプロセスに疑問を呈した他の(日本人)評価委員たちの意見も、実質的にはこの原理的批判に通底するものを含んでいるのではないか、と思われるのである。
おそらく社研自身が、「全所的」に一つのプロジェクトを遂行することのディレンマを自覚し苦悩しながら30年間歩んできたのであろう。それを原理的に批判するか、方法論の次元で批判するか、意見はそれぞれだが、いずれにせよ今後のプロジェクトについては社研内部で新しい方式を模索中であるというから、いずれこれらの批判に対する答えは出されるものと期待する。
なお、この際、後述するような国際交流の実績を活かして、国際的な観点・意見を踏まえたテーマや参加メンバーの選定が行われることが重要であろう。「脱亜入欧」問題もその過程で十分議論されることを期待する。
3 人事構成について
「日本社会研究」を目指すためには、人事構成にやや偏りが見られる、手薄な分野がある、といった評価を下す向きが少なからずあったことは銘記すべきであろう。ただ、限られたポストで、「社会」のあらゆる分野にまんべんなく人員を配置することは難しいし、無理にそれをして却って弊害を来すことにもなりかねない。むしろ、これも複数の委員から指摘されていることだが、客員研究員招聘や任期制による流動的人事などで欠を補う道を積極的に探る必要があろう。この点からいっても、客員研究員(客員教授・助教授)のポストを、第1種~第3種いずれについても、国に対してもっと要求するべきであろう。
4 国際交流・協力活動について
社研がこれまでに受け入れてきた外国人研究員・研修員の人数の多さと顔触れの多彩さに象徴されるように、日本社会研究の面における国際協力への貢献度には評価委員の大部分が称賛を惜しんでいない。
また、英文雑誌 "SSJJ" についても評価が極めて高いし、インターネットを利用した "SSJ-Forum" に対する評価も高い。日本社会研究情報センターの設置及び運営についても、更なる改善を望む声はあるものの、基本的には肯定的評価を受けたといってよい。
その他、国際協力の対象としてアジアにもっと重点を置くこと、特に情報の伝達に関してアジア諸国の経済的ハンディキャップに配慮すべきだという指摘があったことには、今後社研として十分留意すべきものと思われる。
しかし、何よりも強調しなければならないことは、国際協力活動のためのインフラストラクチャーの貧困ぶりに、(日本の国立大学の貧しさをよく知っている評価委員たちでさえ)あらためて驚愕したという事実である。もちろん、これは社研の責任でも東大の責任でもなく、日本の高等教育・学術政策の貧困の直接的反映なのだが、それにしても社研としての改善への工夫の余地はありはしないか、というのが大方の実感ではなかろうか。
5 教育への参加について
研究所の所員は研究に専念すべきで、学部教育にあまりコミットすべきではない、という点では大方の意見が一致したといってよい。しかし大学院、特に(後期)博士過程の教育に従事することの意義を指摘する向きも多かった。
なお、教育参加の文脈においても流動的人事の有用性を指摘する委員もあったことは注目に値する。
6 将来構想について
将来構想については、社研自身がはっきりと提示しているわけでもないし、評価を依頼しているわけでもないから、この項目を立てること自体適切ではないかも知れない。しかし、さまざまな面に即して社研の現状を視るにつけ、「社研よ、いずこへ?」という疑問が湧いてこざるをえなかった。
現在は「日本社会研究」とされている社研の研究活動の「中心的課題」を将来どうするか?、全所的プロジェクトをはじめとする研究活動をどの範囲の研究者の参加を得、どのようなプロセスを踏んで進めるのか?、国際協力活動の目標なり重点なりをどこに置くか?、人事のやり方は?、大学院教育のあり方は?、等々どれをとっても、将来構想の一環として考えざるを得ない問題である。
存在理由が(少なくとも従来は)ほとんど自明な「学部」や特定分野の研究を設置目的とする研究所と異り、(京都大学人文科学研究所などと同様に)社研の場合は、それ自身内包・外延ともにはっきりしないジャンルの研究機関たることをを標榜するだけに、常に自己の歩むべき道を探り、しかもそれを外へ向かって発信していかなければならない宿命にあるのではなかろうか。
この点、ある評価委員が「日本で唯一の国立の社会科学研究所として、東京大学の枠を離れて大きく飛躍することを検討課題」とすることを勧めているのは注目に値する。上述のようなさまざまな面で将来構想を立て、実現していくのに必要な資源をどうやって調達するか?、定員、予算、インフラストラクチャー等に関する貧困を打開するにはどうすべきか? こうした問題が深刻なだけに、より一層真剣な検討が所内で行われる必要があろう。
もちろん、(日本の中では比較的)大きな蓄積・資源とすぐれた同僚をもつ大学にいることのメリットは計り知れないから、軽々な判断は慎まねばならないが、いずれにせよ、冷徹な計算と言葉の真の意味でラディカルな発想が求められるところである。