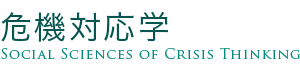「安全」と「コミュニティ」への期待が見えにくくするもの
「リスク」と対置される概念は?
「リスク」の反対は何か、と問われたら、何を思い浮かべるだろうか。「安全」と答える人は多いだろう。しかし、社会学者のN.ルーマンは、「リスク」に対して「危険」を対置している。
「リスク」という語には様々な用法があるが、これは独特な使い方である。未来の損害は不確かである中、起こりうる損害が自らの現在の決定の帰結であると捉えるならば「リスク」、自分以外の外部からもたらされると捉えるならば「危険」と区別する(Luhmann 1991=2014:38)。考えられる選択肢の数が著しく増大した現代では、他の選択ならば他の結果がもたらされたに違いないとの見方が強まることから、リスク現象を誰に・何に帰責するかが社会の中で複雑に争われる。そこで「リスク」/「危険」の区別を用いることにより、「何が」リスクであるかではなく、人々がリスクを「どのように」扱い合っているかを観察することが可能になり、「リスク」の社会的行為としての側面を分析しうるようになる。そこに、この区分を用いる意味がある(小松 2003:29-34)。
「地震によって家が倒壊したり人が死亡したりする可能性に対して、(...)リスクと危険のどちらも適用できる」ことは、ルーマン自身が例に挙げている(Luhmann 1991=2014:43)。「地震の起こりやすい地域から転居」するという決定によってリスクを回避することも原理的には可能なのであり、「リスク」か「危険」かは内容に依存しているわけではないと指摘する。
ところが東日本大震災後には、この「転居」という決定をとるか否かは、原理的どころか多くの世帯が現実に直面する選択となった。津波で家を失った後にもう一度元の土地に住宅を再建することは、「リスク」/「安全」の図式に基づくならば、「リスク」をとったことと見なされうる。しかし、そのようなみなし方は、再建を目指している被災者にどう映るか。
「安全」の追求を至上とする世論がもたらす潜在的な副作用を、「リスク」/「危険」という区別がどのように相対化できるか、希望学・危機対応学で長く関わってきた釜石での観察から考えてみたい。
「リスク」/「安全」の図式が見えにくくする葛藤
我々のチームは震災時に釜石市A地区に住んでいた50ほどの世帯に毎年聞き取りを続けている。東日本大震災で甚大な被害を受けたA地区では、盛土を伴う土地区画整理事業(以下区画整理)が続いており、震災から7年以上が経った2018年5月現在も各世帯への土地の引き渡しは完了していない。つまり、自分の土地であっても家が建てられない。
危機対応学プロジェクトと縁の深い、東大社研編『持ち場の希望学』(2014,東大出版会)の拙稿でも取り上げた、A地区で被災してA地区での再建を目指しているZさんの以下の発言を、本稿では視点を改めて考えてみる。
東京から来たボランティアの人に、「なんでそんな危ないところに住むんですか」って言われたことがあるんですよ。多分こういう海のそばにいない人は、だったら引っ越せばいいじゃないと思うんじゃないですかね。でも、引っ越せばいいということではないんですよね。
海の近くに行くのは怖いと私も今も思うんですけど、でも海が悪いわけではない。やっぱり元の地区が好きだと思うので。思いというのはやっぱりみんなあると思うので。
この発言をどう解読できるだろうか。後半の「元の地区が好きだ」という言葉は、「愛着」と受け取られやすい。そしてボランティアの人は、こんな危ないところに住むのは「リスク」を犯している、とZさんの選択をみなしている。その場合、再度海のそばに住むことは、「安全」と引き換えに「愛着」を選んでいるのであり、それはすなわち自己責任で「リスク」を負っているのだ、と意味づけられかねない。しかし、Zさんはそのように理解してほしかったのだろうか。
そもそも震災前は、持家のあるA地区から大地震に備えて転居することは、原理的に可能とはいえ、実際は想像の範囲外にあったと考えられる。津波が来るかもしれない地区であることは、自分たちにはどうにもならない自然のせい、つまり「危険」であった。
しかし、東日本大震災は、A地区に住むことが他者からどう解釈されるか、その可能性の選択肢を複雑にした。将来再度津波が来る可能性のあるこの地区に住宅を再建することは、地元を愛するがためにポジティブな「リスク」をとった自己決定と解釈される可能性もある。だが、現地の事情を知れば、地元以外の土地への転居が経済的に無理であるために仕方なく決定した、消極的な「リスク」でもありうることがわかる。
A地区で調査を続けている中で、気になっていることがある。復興事業により住宅再建を一番待たされているのが、世帯主が40・50代の働き盛りである核家族世帯のようである点である(西野他 2018)。収入もあるが出費も多いのが中高年である。復興住宅に入るには収入が高すぎるが、復興事業が行われずにすぐ家を建てられる非浸水地域に新しい土地を買うには資金が足りない。だから元の土地での住宅再建を予定しているが、土地の引き渡しに時間がかかっているため、震災後7年の時点でも仮設住宅で区画整理を待っている、そんな世帯が複数ある。中高年の一人であるZさんが上記のように語ったのは2012年だが、転居という「安全」を選ぶには資金不足であることが見えていた上で、「引っ越せばいいということではない」と発言しているように思える。
さらに、A地区の復興事業を、高台移転ではなく、区画整理+防潮堤という現地再建の手法で行うという行政の決定は、Zさんらがかかわったものではない。その意味でも、A地区での再建は、移転という選択肢を与えられなかったための「危険」としても語りうる。
しかも、事業に時間がかかればかかるほど、戻ってこられない人が多くなる。実際に、親と二世帯住宅にすることで再建資金を調達するつもりだったが、高齢になった親が仮設住宅で待ち続けることができなくなり、再建を諦めたケースや、7年のうちに子どもが成長し、大学の学費と住宅ローンの二重の負担を躊躇せざるを得ないケースがある。これだけ事業に時間がかかることは、Zさんら自身の決定の帰結とは言えない。
Zさんは、自分たちの状況を押し付けられた「危険」として語ることを抑制しているが、主体的な「リスク」をとっているとされることにも躊躇しているように見える。Zさんのみならず、再建の判断は、誰がどの文脈でどちらの語り方をするかで、主体的な投企による希望にもなれば、責任の押し付け合いにもなりうる。その危うさに、お互いが気を遣いつつも、戸惑い、揺れ動いていることを、被災地の人達は知っている1。
被災当事者ではない外部の人が「リスク」/「安全」の図式を自明視することは、今回の例のようにボランティアとして接点を持った時にのみ、被災地の人に影響するわけではない。大矢根淳は、「被災地外の人々は『被災地(者ではなく)のことを思って』優しく、正しく『復興まちづくり』を唱えるが、この言葉が当の被災者には『被災者の追い出し』と聞こえるのである」(太字箇所は原文では傍点)と指摘する(大矢根 2007:19)。災害に強い街を再建することが「安全」に資すると思えばこそ、単なる「復旧」ではなくよりよい未来の町を生み出す「復興」が望ましい、危機を未来のためのチャンスに――このような総論を世論は支持する。現地のジレンマを知らない被災地外の善意のまなざしが、大規模な公共事業を後押しし、知らぬ間に元の地区に戻れない人を増やしている、との指摘である。大矢根は、震災前の木賃アパート群は安全な新築マンションにかわり、住人は家賃を払えずに元の地区に戻れなかった阪神淡路大震災などに見られた状況を描いているのだが、盛土を伴う大規模な復興事業の長期化により家が建たない人達が出てくるA地区の例にも当てはまる。その総論の先には、「安全」だけで将来を決定することはできない、個々の被災者の生活の実際がある。
あるコミュニティの出現
被災地をめぐっては、「コミュニティ」が果たす役割に向けられる期待も大きい。しかし、それらの期待に応えることは現実には難しいとの指摘も頻出する。個々の被災者からはどのように見えるだろうか。
遡ること23年、筆者は阪神淡路大震災の発災時は大学生だった。大学院に進学し、A地区のように震災復興に伴い区画整理が行われた神戸市のB地区で、社会調査に携わった。
誰しもが早く家を建てたかった。だから区画整理に反対する住民もいた。しかし、揉めて遅くなるよりは、区画整理を受け入れ、むしろプロセスを早く進めるために尽力することを、この地区は選んだ。神戸市の場合、住民合意のプロセスとして住民側からまちづくり提案を提出する必要が制度上あり、そのとりまとめに奔走する住民たちが現れた。
大都市の例にもれず、B地区も住民同士のつながりが強かったわけではない。区画整理により運命共同体として人工的に一つに括られたと言っても過言ではない。しかし、本当に危機に対応しなければならなかったこの時期、まちづくりの担い手たちがしっかり出現したのである。その中心は40代くらいの働き盛りのサラリーマンたちだった。既存の自治会――震災後は活動を休止していた――では活動していなかったが、新しい「まちづくり協議会」に集った。
仕事が忙しい年代だが、震災から数年の間、ほぼ1週間に1度は平日の夜に集合して、議論を重ねた。さらに、市内・市外各地の仮設住宅に四散している住民に手作りの会報を送って地区の状況を知らせたり、震災前には無かったお祭りを始めて、離れている住民がB地区に集まるきっかけを作ったりもした。まちづくり協議会は、「一日でも早く、一人でも多く」(B地区に帰って来られるように)というスローガンを掲げた。そうした活動を通して、B地区という範囲は一つの「コミュニティ」として住民にみなされるようになっていったと言える。B地区に戻ることが復興である、と筆者らに語る人もいた。当初は人工的な擬制であったはずのB地区という括りが、自身の復興の基準として――社会学で言うところの準拠集団として――機能し始めたのである。
危機対応のためにコミュニティを作るのか
さて、ここからが本題である。神戸のB地区では震災から7年で区画整理が完了したが、それまでにはまちづくり協議会の活動への参加者は目立って減っていった。そして、震災後約8年の時点で、復活した自治会内の一組織となる形で、まちづくり協議会の活動は一区切りがついた。
同じ頃、震災後盛んになった各地のコミュニティ活動が衰退してきた、との指摘が地元の新聞などでも見られた。「コミュニティ活動の低下は、平時に戻った証拠」との趣旨の言葉を現地で聞いたことが印象に残っている2。
このことをどう評価するだろうか。せっかく生まれた地域の結びつきをもっと活かすべきだという声が聞こえてきそうである。たしかに防災の分野では、地域コミュニティの日頃の活動を通じて非常時に備えることに期待する意見が多くみられる。しかし、生業を通して生計が居住地と結びついているわけではない都市生活者に、非常時のために平時からコミュニティ活動を、と期待することは難しいと筆者は考える。働き盛りのサラリーマンは、非常時を過ぎたら職場中心に戻らざるを得ない。
コミュニティに関心を払わない、生活の「私化」を嘆く声はある。しかし、私たちは非常時のために平時の生活をしているわけではない。そのことを踏まえて「コミュニティ」を語らなければ、現実味を欠くことになる。だから、B地区の活動が下火になっていったことは、活動を担っていた個々の住民から見れば合理的な行動であり、非難されるいわれはないはずである。
B地区の活動は、都市計画の制度によって強制された地域性と、努力して生み出された共同性を背景に持つ点では「コミュニティ」だが、区画整理の早期実施という目的のために活動したという点では、むしろ「アソシエーション」的である3。老朽化に伴い、建て替えを調整しなければならなくなったマンション住民のようでもある。そもそも、町内会の原型の一つは急激な都市化に対する「共同防衛」として住民が自発的に結成したアソシエーションだったという玉野和志のような指摘もある(玉野 1993:184)。もちろん、何らかの目的に基づく機能的な活動から、B地区のように「コミュニティ」としてのまとまりが生まれることもある。町内会の仕組みも今に続く。ただし、共同防衛から生まれた活動が平時の包括的な協力や親睦を旨として続いていくことは、必然ではない4。
さらに言えば、その逆、つまり「コミュニティ」と呼ばれるような平時の地域のつながりが、非常時に共同防衛の機能集団として動くことも必然ではないのではないか。2000年代に入って、町内会が行政機能を補完する「協働」への期待、特に非常時の共助機能への期待は高まっている。しかし、つながりはあくまでつながりであり、それが平時を超えて何らかの機能を果たすと想定することは、実は原理の異なるものをつなげている可能性がある。
生活は危機対応のためだけに構成されているのではない。非常時のために新たな土地を求めて転居しないことを主体的な「リスク」とすることが理不尽であるように、非常時の備えを考えれば人々が平時のコミュニティ活動に参加するはずだ――参加しない人は「リスク」を犯している――と想定することも危ういだろう。
そうするべき理由がある時には人々は協調行動をとる――それでよしとするしかないのではないか。そのような個人の合理性にあえて目を向けなければ、「コミュニティ」への過剰な期待のみが膨らむように思える。
本エッセイでは入口しか描けなかったが、「リスク」/「安全」という図式では掬い取れないような生活再建の複雑性やコミュニティへの期待過多を、被災者個々人の視点から多角的に描き出すことは、危機対応を考えるための基礎作業として社会学が果たせる役割の一つだろう。
文献
小松丈晃,2003,『リスク論のルーマン』勁草書房.
Luhmann, Niklas, 1991, Soziologie des Risikos, Walter de Gruyter.(=2014,小松丈晃訳,『リスクの社会学』新泉社.)
西野淑美・石倉義博・平井太郎・秋田典子・荒木笙子・永井暁子,2018,「質的縦断調査と質問紙調査からみる東日本大震災後の住宅再建判断―岩手県釜石市A地区世帯を対象に―」『日本都市学会年報』51.
大矢根淳,2007,「被災地におけるコミュニティの復興とは」浦野正樹・大矢根淳・吉川忠寛編『復興コミュニティ論入門』弘文堂.
佐藤慶幸,2010,「コミュニティとアソシエーション―マッキーバー」日本社会学会編『社会学事典』丸善出版,48-49.
Solnit, Rebecca, 2009, A Paradise Built in Hell, New York: Viking.(=2010,高月園子訳『災害ユートピア』亜紀書房.)
玉野和志,1993,『近代日本の都市化と町内会の成立』行人社.